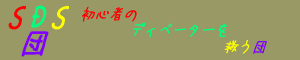証拠資料についての総論的考察
ここでは、普段あまり意識せずに扱いがちな証拠資料について、なぜ証拠資料が必要なのかという原則論から、いかにして証拠資料を扱い評価するかという実務までを、ジャッジと選手の両方の立場から筆者なりに考察しています。証拠資料の扱い方は究極的にはディベーター各自の意識に依存する問題です。これを読まれることによってディベーター各自が証拠資料について考える機会をもつことにつながれば幸いです。
はじめに
本稿は、ディベートにおける「証拠資料」の扱い方について体系的に記述することを目的としています。これまで、リサーチの方法や証拠資料の有効なつぶし方といった「テクニック」についての興味関心はあったものの、証拠資料の必要性やその扱い方については、必ずしも十分な考察がなされてこなかったように思います1)。そこで、ここでは、テクニック以前の問題である、証拠資料を扱う際の心構えや、証拠資料に関係する種々の論点について、細かな部分も含めて考察していくことにします。
以下で述べるとおり、競技ディベートを行うにあたって証拠資料はほとんど必要不可欠な存在です。であるにもかかわらず、なぜ証拠資料を使わなければならないのかということや、証拠資料を使用するに当たって注意すべき点ということがあまり考えられてこなかったのは、証拠資料の存在がディベートという競技の枠組みの中でどのような位置づけにあるのかという意識が欠けてきたからではないかと思っています。というわけで、本稿では証拠資料が政策ディベートの中で果たす役割について私なりに考えた結果を中心として、そこから導き出される帰結という形で証拠資料の扱い方を説明していくこととします。
ここで、本稿の大まかな流れについて簡単に記しておくことにします。
最初に、政策ディベートにおける証拠資料の意義と、そこから導かれる証拠資料利用の大原則について考察をしています(第1章)。論考の中で最も重要な部分と言ってよいでしょう。
次に、そこから導かれる、証拠資料が満たすべき要件について議論します(第2章)。証拠資料の出典や証明力、適切な引用か否かという問題を取り上げています。
これを踏まえて、試合の中で証拠資料をどのように用いるべきかについて、主に選手の立場から説明しています(第3章)。ここでは、引用のマナーや証拠資料の提示請求をテーマにしています。
最後に、ジャッジの資料提示請求や、ジャッジが試合中に読まれた証拠資料をどのように評価すべきかについて私見を述べています(第4章)。ここでは、疑義のある証拠資料に対するジャッジからの提示請求や、証拠資料の証明力判断に関する様々な問題を論じています。
以上の議論が示すのは、証拠資料の使用が単なるディベート技術や説明の方法だということではなく、政策ディベートの枠組みを形作る重要な要素であるということです。すなわち、政策ディベートの中で「メリットを出さなければ肯定側は勝てない」と考えることと同様に、証拠資料を適切に使用しなければ試合で勝つことはできないということです。もっとも、この「適切さ」には、資料を要しない議論という考え方も含まれています。
以下の記述は、このような理解に基づいて書かれています。あくまで私見の域を出るものではなく、批判の余地は少なくないとは思いますが、何らかの形で参考になれば幸いです。なお、本稿で使用している用語の中には筆者が独自につけたものがあります(「再現可能性の原則」など)ので、一般的なディベート用語ではない場合があります。その点はご注意ください。
第1章 総論
1.1 証拠資料とは何か
§1 証拠資料の定義
証拠資料とは、一般には「ある事柄の真実性を証明するために用いられる資料」のことを指します。これを特にディベートにおいての用法に即して定義すると、以下のようになるでしょう。
『証拠資料とは、肯定側・否定側のそれぞれの主張についてその説得力の評価を確定するための材料である』
*証拠・資料の意味はそれぞれ以下のとおり(広辞苑)
【証拠】
1)証明の根拠。事実認定のよりどころ。あかし。証左。「論より―」
2)裁判所が法律を適用すべき事実の有無を確定する材料。
【資料】
1)もとになる材料。特に、研究・判断などの基礎とする材料。「―収集」「参考―」
2)試行(同一または同一とみなされる条件で何回も繰り返すことができ、結果が偶然的な、実験・観察・調査)の結果。または結果を数量で表したもの。
ここで、以上のような定義によれば、説得力の評価は証拠資料によらなければ確定できないことになるのではないか? という疑問が沸くかもしれませんが、以上のように考えたとしても、証拠資料の有無によって主張の評価が全て決するわけではありません。あくまで証拠資料は議論評価の一材料であって、議論の種類や文脈などによってその位置付けは大きく異なってきます。ですから、証拠資料がなくても説得力ある主張が可能な場合がありますし、証拠資料が何の意味も持たないような主張も世の中には存在します2)。
ただし、競技ディベートが客観的な説得力を競うものである以上、証拠資料の位置付けが低く評価される機会はあまり多くありません。これについては、ディベートにおける証拠資料の意義というテーマで、すぐ後に説明します。
§2 証拠資料の意味
競技ディベートの重要な原則として、二つの重要なポイントを挙げることができます3)。一つ目は、ジャッジが可能な限り予断を廃して議論を評価することです。二つ目は、試合で出される議論は全て中立のものであり、ディベーターの個人的見解に還元されてはならないということです4)。
以上の原則から導き出されるのは、ディベートが競技者に対して客観的な説得力を有する議論を要求しているということです。これは、競技としての公平性に基づく要求であると同時に、教育的な見地からも正当化されるものです。すなわち、ディベートでは両チームが公平に評価されなければ試合になりませんし、またそうした環境の中でこそ議論の訓練が効率的に可能となるということです。また、ディベートに期待される教育的効果は、客観的な根拠に基づく論理的思考の養成であるということもいえます。
こうした事情を踏まえると、ディベーターが自らの主張を正当化するためには、みんなが共有できるような一般常識(もっとも、一般常識とはどの程度の知識まで含まれるのかという判断は困難です。これについては4.2で論じます)から導かれる論理的帰結のみで議論を行わねばならないということになります。
しかし、政策ディベートで扱う政策論題は、一般の生活とは乖離したテーマです。こうしたテーマを議論する際には、専門的な知識を避けて通ることができません。ですから、一般常識だけで議論を成立させることは難しいし、政策論題を一般常識の範囲だけで議論することに大きな意味があるとも考えられません。それでは政策論題を扱わなければよいではないか、ということにもなりそうですが、政策論題は事実の評価から価値判断までを扱うことができ、教育的にも競技的にも有意義なテーマです。また、民主主義社会に生きる私たちにとっては、政策論題で提示される論点を無視することはできません。日本人に求められる能力は、政策論題をディベートできるような思考力であると言っても過言ではありません。
政策論題をディベートで扱うには、議論の前提となる一般常識の程度を、少なくともその試合に限って、しかも公平な形で補充する必要があります。そこで、そのための手段として、客観的に検証可能な証拠資料による情報の補充が許されることになるのです。これが、ディベートにおける証拠資料の意義です。
このような理解からは、証拠資料は必ずしも必要ではないということもいえます。これには二つの場合があります。
一つは、ディベーターとジャッジの全てが完全に論題についての知識を共有しており、そうした前提のもとで議論を行う場合です。例えば、原子力技術者が組織内部で原子力発電所の危険性について検討するためにディベートを行うという場合は、かなり高い程度の専門知識を仮定して議論を進めることに問題はないでしょう。
とはいえ、原子力技術者として必要な「議論の能力」を高めるなどの目的でディベートを行う場合には、やはり教育的見地から客観的な証明を求めるべきでしょう。それと同様に、政策ディベートにおいては、ディベーターやジャッジ、観客の知識などに関わらず、一般常識から乖離した部分について証拠資料の使用が求められる必要があります。また、このような状況は競技ディベートには当てはまりません。議論の前提としてどの程度の知識が含まれるのかは、議論の当事者が帰属する集団の属性に依存しますが、競技ディベートでは、あくまで「ディベートを行う」という集団でしかないため、論題について共有できる専門知識を有しません。また、競技ディベートはそのような属性を否定し、証明の過程を競技の一内容としているのであって、その意味でも上述のような状況は発生しないのです。
証拠資料を必要としないもう一つの場面は、主張内容が特別の証明を要しない一般常識に含まれたり、合理的な推論によって十分説明できる場合です。例えば「食べる物がなくなったら人はいずれ死ぬ」ということについては、特に説明を要しないでしょう。このような事実までいちいち証明を要求するとすれば、ある国への食糧支援を検討する際に、食糧不足によってどのように人が死んでいくのかといった、主題から大きく外れた議論に時間が割かれ、議論の質がかえって低下してしまうことになります。そんなディベートは教育的ではないし、面白くありません。よって、証明を要しない、あるいは証明を省略してもよい議論も存在するといえるのです。
しかし、この場合にも私たちは証拠資料の必要性を過小評価してはなりません。なぜなら、ディベートではあくまで公平中立の立場から議論を見る必要があり、それは同時に常識という見解からも一定の距離を取ることを意味するからです。ディベートの魅力は、客観的に適切な証明を伴うことによっていかなる見解をも支持できるという自由度にあります。常識的な見解のみが評価されるようでは、ディベーターの仕事は、既存の常識をとにかく収集し、それを忠実に再現することになってしまいます。これでは、批判的思考なんて理念を貫くことは困難ですし、さらに言ってしまえば、ディベートを行う意味がないといっても過言ではないでしょう。
では、ディベートにおいてどういった議論に証拠資料が必要とされるのでしょうか? 実は、ここに決まった答えはありません。あえて答えるとすれば、それぞれのジャッジが求める証明の水準は異なるということになります。ジャッジは、両チームに対して公平である限り、自分の中に立証を要する基準を設けます。ジャッジが証明されたと感じるかどうかが、証明されたかどうかの基準です。「ディベートではジャッジに判定が委ねられている」というのは、そういうことです。
しかし、こう説明するだけでは、ディベーターにとってもジャッジにとっても、証明の基準や証拠資料の要・不要を考える手掛かりにはなりません。そこで、もう少し詳しく説明してみます。
ディベートの中においても一般常識が通用することについては、異論はないでしょう。だとすれば、常識に沿った主張(いわゆる「公知の事実」や「経験則」)については、特別の証明が無くてもとりあえずは評価するという立場を取るのが合理的です。ですから、ジャッジはまず聞いた議論の中で特別な知識を要さずに納得できる限りで議論を評価します。
しかし、ジャッジは最終的に試合を判定する際には、議論において重要となってくる諸論点について、証拠資料による最低限の客観的証明が与えられているか、すなわち立証責任を果たせているかを検討する必要があります。この段階においては、最初に出された段階の評価だけではなく、相手の反駁も踏まえて、議論全体としてどのように評価されるかが問題となります。
このとき、ジャッジはいわゆる「証明の強さ」というものを考えます。証明されているかどうかというのは0か1かという問題で表されるほど単純ではなく、例えば「かなり確からしい」という、ほとんど確信に近い評価から「そういわれればそうかもしれない」というあいまいな評価、さらには「極めて疑わしい」といった否定的な評価まで、段階的な評価によって表されます。
こうした評価方法を踏まえると、どうやら次のように考えることができそうです。まず、一般に常識とされる事柄については、証拠資料がなくても最低限の客観的証明が与えられていると考え、その点について合理的な反証が無い場合はとりあえず採用するという態度をとることができます。ただし、証拠資料による証明がない以上、その点について積極的な評価はできないと考えるべきでしょう。
例えば、「原子力発電所が爆発したらたくさんの人が死亡する」という議論は、おそらく正しいものだろうと思われますが、その具体的な数字やプロセスが一般常識として評価できるレベルではない以上、その証明が証拠資料によってなされなければ、この評価は抽象的なレベルにとどまると評価せざるをえません。相手からそうした指摘があれば、なおさらです。
ですから、とりあえずそうだろうと思われる論点についても、証拠資料によって証明を行うことに意味はあります。つまり、ジャッジに対してアピールすることができるということと、相手の反論に対する先制攻撃になるということです。逆に、常識的でかつあまり重要でない論点については、いちいち証拠資料を持ち出す必要は乏しいでしょう。
実際に判定を出す際にも、このように処理されています。例えば、基本的な価値基準である「人命は大事である」といった基準については証明なしでもとりあえず受け入れられます。しかし、その議論の文脈における妥当性を考える際には、それ以上の特別な議論が無い限りは判断を保留し、議論全体の評価の中で必要に応じて判断する――時には評価しない――ことになるのです(いわゆる価値比較などを踏まえて考えます)。さらに、相手から別の説得的な価値基準が出されたときには、そちらを採用することもありえます。
ですから、ディベーターは重要な論点については積極的に証拠資料を用いる必要があります。逆に、試合で特に争点にする必要のない論点については、証拠資料をいちいち用いる必要はないということになります5)。
以上をまとめると、証拠資料は一般常識から導き出される主張に加えて何らかの主張を行う際に要求される、試合における前提の補充であるということができます。ディベートにおいてはスピーチに一定程度の証明責任を要求しており、それによって議論の公平性や教育的効果を高めようとしています6)。ですから、競技ディベートにおいて証拠資料の存在は重要であり、特に政策論題を扱う際には必要不可欠であるといえるのです。
1.2 証拠資料の満たすべき原則
§1 再現可能性の原則
前節で述べたとおり、証拠資料の意義は試合における前提の補充です。しかしながら、試合の前提として仮定することができるのは、原則として相手チームやジャッジにも共有可能なものである必要があります。例えば、試合会場に行く途中の交差点で聞こえた噂話を紹介したところで、そもそもそんな噂話があったかどうかも分からないのですから、人を納得させることはできません。
このことからも分かるように、証拠資料は、本当にそのような資料が存在するのかということが他の人に対して明らかにされていなければ、証拠として提出することはできません。ここでいう「明らか」とは、どこに行けば証拠資料があるのかがきちんと理解できるということです。
ここから、証拠資料として提出されるために、二つの条件が要求されていることが分かります。第一に、きちんとした形で保存されたものであるということです。第二に、それが誰にでも確認できる形で存在しているということです。これらが満たされていることによって、その証拠資料が本当に存在するものであるかを後から確認することができますから、相手チームやジャッジは安心して証拠資料の内容を共有することができます。つまり、証拠資料が本当に存在するということ、真実のものであるということを保証する要素として、こうした要素が望まれているのです。
以上を簡単にまとめると、証拠資料は誰にでもアクセス可能なものである必要があるということになります。少し難しい言葉を使うと、証拠資料は再現可能でなければならないと表現できます。ですから、このことを「再現可能性の原則」と呼ぶことにしましょう。
§2 証拠内容尊重の原則
証拠資料は、主張を導くための前提を提供するものです。ですから、前提となる内容そのものが重要な意味を持ちます。どのような前提が補充されたかによって、そこからどのような主張が新たに導かれ、また導かれないのかが決まってくるからです。
従って、証拠資料の評価は、あくまでその証拠資料が与える情報によって決まるのであって、その存在自体によるものではないということになります。このように、証拠資料をその内容を踏まえて評価する態度のことを、「証拠内容尊重の原則」と呼ぶことにしましょう。
(反対に、証拠資料の存在のみをもって証明がなされたと形式的に判断することを「証拠形式尊重の原則」とでも呼ぶことにします。後述の通り、この原則は誤っており、採用されるべきではありません。なお、証拠形式にこだわることは、その裏返しとして、証拠資料による証明が必要ない部分についても証拠資料がなければ評価しないことになりがちであり、その意味からも望ましくありません)
証拠資料があるかないかだけに着目する証拠形式尊重の原則は、「とりあえず証拠資料を読めばいい」という結論につながります。そうなってしまえば、証拠資料の実質的な意味は失われ、結果的に議論の質を低下させることになります。ですから、証拠資料の評価については、その内容にまで踏み込んで審査するべきである、つまり、証拠内容尊重の原則が貫かれるべきだといえます。
は、証拠内容尊重の原則でいう「証拠内容」とは、いかなるものでしょうか? 証拠形式尊重の原則と対比させた意味では、証拠の文面ということになります。しかし、証拠内容は単なる文面ではなく、その文面が主張されている文脈、主張者の権威性や思想7)。、表現媒体など、付随的な属性をも含みます。それは、私たちがある見解を判断する際には、それがいかなる立場の人物によって主張されているかということについても判断を加えることからも理解できるでしょう。もちろん、そうした要素は文面の内容に準ずるものでしかありませんが、主張の内容によってはその比重が大きくなることがあります。詳しくは証明力の概念を説明する際に議論します(2章2節)。
さて、証拠内容尊重の原則からは、引用した証拠資料の内容が評価されるということになります。この証拠資料の内容は、引用された論点とは独立に存在します(証拠資料で言われていることと主張として挙げていることは、独立に評価されるということです)。この内容については、引用された論点の中でしか理解できないわけではありませんから、特に断りがない以上、別の論点を考える際に応用してもよいことになります。すると、証拠資料は引用された論点だけでなく議論全体の判断においても影響を及ぼすということになります。特に、本稿のように証拠資料の効果を前提の補充と考える立場からは、これは当然のこととして導かれます。
以上の議論から、ある論点で用いられた証拠資料は、いわゆる交差適用(別の論点に既出の証拠資料が援用されること。Cross Applicationといいます)なくして別の論点に適用されうるということになります8)。一方で、これを無制限に認めるならば、ジャッジによる議論の再構成、すなわち恣意的な介入を認めることにつながりかねません。これを防ぐために、あくまで証拠資料は引用された論点でのみ機能するという立場を取ることも可能ではあるでしょう。しかし、それでは同じ証拠資料が適用される論点について「ここでも〜の資料が当てはまります」という必要があることになります。つまり、そうしたコメントがない場合は証明がなかったと考えることになるわけですが、それでは形式的なコメントがあるかないかで証明の有無を決するわけになりますから、先に否定した証拠形式尊重の原則を採用したのと同じことになってしまいます9)。
それでは、このような場合をどのように判断すればよいのでしょうか。ある部分で読まれた証拠資料から選手の意図しない議論を作り出すことは、いうまでもなく恣意的な介入であり、無効です。しかし、証拠資料の内容に矛盾がある場合など、指摘が無い場合でも資料の内容について比較検討し、異なる論点の間で調整がなされることは一般的に珍しいことではなく、またこれは一般的に議論への恣意的介入とは見なされません。この理由は、そうした調整が試合中に出された以外の論点を形成するものではなく、あくまで試合中に出された議論の評価にとどまるからです10)。
よって、証拠内容尊重の原則及び証拠資料の意義とジャッジの恣意的介入防止の要請を踏まえた上で、次のような帰結を導くことが許されるでしょう。すなわち、ジャッジは試合中に適切に出された証拠資料を判断材料として採用し、試合中に出された論点の評価について自由に用いてよいということです。これについては、後でも述べます(4.2)。
また、証拠内容尊重の原則は、反論の無かった資料に対しても実体的な評価を要求することになります。すなわち、ある反駁(一個の主張とそれに対応する根拠を含む)に反論できなかった(ドロップした)場合でも、それによってその主張をそのまま受け入れなければならないということではなく、反論できなかった根拠の内容と、それによって裏付けられた限りでの主張を受け入れるということです。よって、再反論がなかったからといっても、その反論が全面的に認められるわけではなく、あくまで当初の証明のまま認められるだけにとどまるのです。
(なお、この論点はいわゆるタブラ・ラサやクリティック・オブ・アーギュメントのような判断枠組みに関する理解とも関係がありますが、ここでは詳述しません11)。)
§3 違法証拠排除の原則
再現可能性の原則の部分でも述べましたが、証拠資料は現実に存在する必要があります。ディベーターが誤った前提12)を試合に持ち込むことは、競技的見地からも教育的見地からも許されません。ディベートという競技は客観的な事実に依拠して行われることが大前提であり、それによって公平性が保証されていますから、そのような世界に仮想の前提が持ち込まれてしまえば、公平な議論は不可能になってしまいます(対戦相手が、架空の大学教授をでっちあげて作った、都合のよい資料を引用してくることを想像してみましょう)。また、現実にない根拠に基づく議論をさせること自体が、教育的にも悪影響を及ぼします。ですから、ディベートにおいて現実に存在しない証拠資料を認めてはならないのです。
もし誤った前提が試合のなかに持ち込まれたとしたら、そうした前提は判断材料のなかから除外される必要があります。このように、誤った証拠資料の使用は厳に戒められるべきであり、そうした証拠資料は議論の評価から除外するべきであることがいえます。これを「違法証拠排除の原則」と呼ぶことにしましょう。
さらに進んで、故意に誤った前提として違法な証拠が持ち込まれた場合には、そのような行為は競技者としての資質をも疑うものであり、倫理的に許されません。それだけでも、少なくとも当該試合において勝利する資格はないと断じてよいでしょう。さらに、誤った証拠資料の使用を抑止するという目的、またジャッジング手続の廉潔性を維持するという目的からも、重大かつ悪質な違法証拠の利用は、当該証拠資料の排除のみならず、使用したチームを敗戦にすべき理由になるというべきです。違法証拠排除の原則は、その名の通り違法な証拠を判断基底から排除することだけでなく、違法な証拠の使用が投票理由になりうることをも含んだ概念なのです。
違法証拠排除というときの「違法」とは、形式的にはルールに反したものという意味ですが、実質的には証拠資料の本来の意味を何らかの意味で歪曲したものという意味をもちます。より正確に表現するなら、証拠資料の引用によって本来の意味との同一性を損ねている場合を指します。
よって、資料の実質的意味を変更するような引用方法や、文面の改竄、また不適切な中略なども、ここでいう違法として処理されることになります。上のように中略や引用箇所の恣意的選択をも違法に含めるのは、前述した証拠内容尊重の原則からも理解できます。すなわち、資料は文面そのものではなく、そこに含まれた意味が評価対象となっているのであって、その意味を変えることは許されないということです。また、存在しない証拠資料を捏造するような場合は、捏造した出典がそもそも存在しないという点で同一性を欠き、またジャッジや対戦相手を錯誤に陥らせるものですから、当然に違法となります。
なお、この違法概念は「違法か適法か」という絶対的な評価によるものではなく、その程度によって相対化されます。実質的にはほとんど意味を変えていない場合や、資料の意味は汲み取っているというような軽微な問題、あるいは形式上存在するにとどまる小さな瑕疵については、資料改竄などに比べて小さい問題であると考えられます。こうした場合には、実質的には違法性を欠くと評価することも可能です。ある資料が違法かどうかという点についても、一般の議論同様、段階的に評価されるのです。このように、違法証拠排除の原則はその違法の程度や様態、試合に与えた影響の大きさなどによって総合的に判断されます。
第2章 証拠資料の要件
2.1 出典
§1 出典の必要性
証拠資料には、その出典が伴う必要があります。この趣旨は、再現可能性の原則(前出1.2§2)に基づくものです。すなわち、資料の内容を議論の前提として受け入れるための要件として、ジャッジと対戦相手にとって共有可能なものであることを示すために出典が必要となるということです。
再現可能性の原則についての部分で説明したとおり、証拠資料を信用するためには、それがきちんとした形で記録されており、実際に第三者が見ることによって検証可能である必要があります13)。これらの要素を満たすため、出典には引用文面と原典の同一性を担保し、適切に指示できる程度の具体性が求められることになります。いいかえれば、出典のみによって第三者がその資料にスムーズにたどりつける必要があるのです。
以上の条件は、証拠資料を採用するための要件です。つまり、出典を満たしたからといって証拠資料がただちに適法になるというわけではありませんし、逆に記録した出典の全てが試合中に要求されるわけでもありません。つまり、出典には証拠資料の満たすべき要件という側面とともに、証拠資料の信憑性や違法性評価に関わる側面もあるのです。
しかし、それらの要素については後にそれぞれ関係する所で議論することとし、本節では証拠資料の最低条件としての出典要件について述べることにします。
ただし、これについても二つの段階があります。すなわち、証拠資料の収集時に求められる記録としての段階と、試合中に提示すべき記録としての段階です。この二つの違いについて、再現可能性の原則からどのような結論を導くことができるかどうかが本節の主要な関心であるということを意識して読まれることで、以降の内容が分かりやすくなると思います。
§2 出典の満たすべき要件
資料の出典を考えるにあたって最初に考えなければならないのは、証拠資料の収集の際にどの程度まで出典を記録する必要があるかということです。ディベーターは試合の準備として大量の証拠資料を収集するが、その際に原典に関していかなる情報を記録しておかなければならないかということは、ディベートを実際に行う上で非常に重要なことです。残念なことに、現状としてこの点を十分にクリアしていない選手が多いように思われるのですが、それは脇に置いておいて、必要と考えられる出典の要素について考察していきましょう。
先に述べた通り、資料の出典にはその同一性を担保し、その資料へのアクセスを可能にする程度の指示性が求められます。ここから考えると、出典を確認するだけでその証拠資料の原典が明らかとなるかどうかがポイントとなります。より具体的にいいかえれば、出典のみをたどることで引用された文面にまで行き着くことができるかどうかが、適切な出典としての要素を満たしているかどうかの指標になるということです。
この点に着目すれば、証拠資料の出典として必要なのは、書籍であればその書名はもちろんのこと、その著者や刊行年をも記録しなければならないということになります。その理由としては、一般に書名だけでは文面を特定することは難しいと考えられるからです。例えば、書籍を検索するためには、書名に加えて著者名やその刊行年を必要とします(図書館などでの資料請求ではそうなっています。もっとも、請求記号の存在などにより、一部のみでも請求が可能なこともあります)。
また、さらに進んで、該当箇所のページについても出典として記録されるべきであるといえるでしょう。これについては、ページ数が無くとも該当部分の特定は可能であるということもいえなくはありませんが、同一性の担保や指示性の確保という要求からは、一見明白に該当部分が発見されるレベルでの特定が求められると考えるべきでしょう。また、そうすることによる実務上の不利益もほとんどないといえます。
雑誌についても同様に考えることができます。すなわち、雑誌資料においてはその雑誌の書名と巻・号・発行年、そして論文のタイトルと著者、該当ページ数が出典として要求されるということです。新聞については、新聞名と発行年月日、該当記事の面数が最低限の要素となるでしょう。もちろん、記事の執筆者がわかる場合はそれも必要となります。
また、近年増加しているインターネットの記事については、その存在が不確定であり、常に移転・消滅の可能性があるという点から証拠資料としての信憑性についても議論がありますが、出典を正しく記録することにより、証拠資料として採用することは可能です。
インターネット記事についても、書籍などと対応させて考えることができます。いわゆるトップページからリンクされるサイトの全部分を書籍とみなし、引用該当部分のページを書籍の一部分として考えるのです。この考え方によれば、インターネットの引用については、該当サイトの名前とその管理者名14)。に加え、該当引用部分の存するページの見出しと文章執筆者、そして更新年月日(サイトはページごとに更新可能なので、該当ページの更新時を記録する)とアドレスを記録することが必要となるでしょう。もっとも、サイトの更新年月日については明らかでない場合が多いので、その点については多少穏やかに解してもよいかもしれません15)。
以上の考察は、再現可能性の原則から導かれる、同一性・指示性の要求を満たすための要件というものです。しかし、証拠内容尊重の原則を延長した考え方からも、証拠資料に対して別の要件を導き出すことができます。
前述したように(1.2§2)、証拠内容尊重の原則は、文面のみならず、それが表現された文脈や著者の属性をも評価するというものでした。この原則を貫くためには、その証拠資料がいかなる立場の人間によって主張されたのかということを特定することが必要となります。この見地からは、証拠資料の出典として、その主張をなした人物の名前とその肩書きが要求されることになります16)。英語で「出典」は“authority”と表現しますが、それはこうした観点によるものだと考えることができます17)。
以上2つの観点は、共に満たされる必要があります。これらをまとめると、以下の表のようにして出典が求められることになります。
| 書籍 | 雑誌論文 | HP | |
| 再現可能性の原則による要求 | 筆者/書名/発行年/該当頁 | 雑誌名+巻号/発行年/筆者/論文名/該当頁 | サイト名/管理者/更新日/執筆者/アドレス |
| 証拠内容尊重の原則による要求 | 筆者の権威性(肩書き)/著者名 | ||
これらの基準は、学術論文における参考資料の引用に要求される条件とほぼ一致しているといえます。ここからも、以上の要件を満たせば、ディベートの証拠資料に対して要求するものとしての厳格性は十分満たしていると考えることができます。逆に、以上の要件を一部欠くような場合は、要件を欠く違法性があるとして、違法証拠と見なす余地が発生します。
ただし、前述の通り、その評価は相対的になされることになりますから、一部の欠如をもってただちに却下しなければならないということにはなりません。だからといって多少不備があってよいということにならないのは、いうまでもないことです(いわゆるマナーです)。
最後に、別の資料を参照・引用している箇所を引用して証拠資料とする、いわゆる孫引きについて検討することにします。これは、実質的には別のところにあるはずの原典を証拠資料として提出しようとしているはずなのに、それが引用されている二次文献の出典を提示する行為です。これが出典の要件を満たすといえるのかどうかが、大きな問題となります。
結論からいうと、孫引きは原則として認められません。なぜなら、証拠資料に出典を求める目的はあくまで原典との同一性を担保するものであり、情報源から離れた二次文献に原典との同一性を見出すことはできないからです。これは、たとえ文面上同じであっても同じことです。もしそれを認めてしまうと、その証拠資料を発表した人の属性や、議論の文脈を無視することになってしまい、証拠内容尊重の原則に反してしまいます。
ただし、二次文献であっても、それが原典に対して独自の解釈を加えている場合や、選択的に引用して論理展開の一部とするなど、それ自体が新たな原典として引用の対象になりうる場合は、孫引きと見なすことは適当ではありません。学問というものはある研究を発展させることによって進歩していくものであり、ある原典に基づく文章が含まれればすべて「孫引き」とされてしまうようでは、世の中の研究は成り立たなくなってしまいます。ですから、それ自体がある資料を引用して構成された独自性を持つ文脈として評価できる場合は、証拠資料として利用することができ、その出典は有効といえます。また、日本語ディベートにおける英語文献の一部和訳や訳書の利用についても、ディベートで用いる公用言語での原典として使用が許されます。
さらに、これに関係して、ある論文がインターネット上に転載されているという場合があります。これについても、孫引きとして出典として認められないと考えられます。ただし、原論文と同一の著者が公開しているというような場合は、再現可能性の原則及び証拠内容尊重の原則に照らし合わせて、実質的な原典と見なすことができるでしょう(通常のインターネット資料同様再現可能性はあり、また著者が同一であることから証拠内容も尊重されている)。
§3 出典の発表
ここまでで出典として記録すべき要素について検討してきましたが、それらを試合中に全て読む必要があるかは別の問題です。証拠資料の要件を誠実に守るという見地からは、先に説明した要素を全て試合中に読み上げることが求められることになります。一方で、全ての要素を試合中に紹介することは、議論の効率を下げることにつながりますし、試合中に紹介されたところで、その出典を試合中に確認することはできませんから、そこまで要求しても意味はないということがいえます。
インターネット資料についてそのアドレスを読むことがナンセンスであることからも分かるとおり、資料としての認識を持つためにスピーチ中で読まれるべき要素は、記録を要する出典の要素より控えめでよいということがいえるでしょう。問題は、スピーチにおいても最低限必要とされる要素はどの程度かということです。これは、証拠資料に要求した要件の趣旨と、試合における効果を踏まえた上で、両者のバランスを損なわないように決められる必要があります。
この節では、「成立要件としての出典」という観点から、出典について検討しています。この観点からは、証拠資料の出典として試合中に発表するものとして最低限求められるものとして、以下の二点の要求を挙げることができます。
一つ目の要求は、その資料を他の資料との関係で独立のものとして認識できなければならないという要求です。これは、再現可能性の原則から導かれる要求を縮小したものです。証拠資料の出典が要求される理由のひとつは、再現可能性の原則から、証拠資料の原典との同一性や指示性を確保し、その正しさを保証するためというものでした。こうした要求から出典が必要とされる具体的な場面は、その資料の内容についてそれを前提として使用するにあたって疑義があるといった場合です。このとき、その評価はスピーチ中に行われるのでなく、スピーチが終わった後、あるいは試合後に別途検討がなされます。ですから、試合中に要求されるのは、後で詳しい出典を基に証拠資料を検討することができるように、試合中のどこで読まれた資料について検討するのか指示するのに必要な出典だけが要件だということになるのです。
ここから、原典と引用文面の同一性を評価するための詳細な出典は、試合中には述べられる必要がないことが分かります。上述の要求を満たすためには、他の資料との関係で当該資料を名指す程度の出典で十分です。
二つ目の要求は、その資料が誰の主張によるものかということです。これは、証拠内容尊重の原則による要求を小さくしたものです。実際に発言者が存在しているということは、証拠内容を評価するための最低限の要素です。権威性については、証拠内容の信憑性を判断するための一要素ですから、引用されなくても証拠内容の文面評価自体は可能です。ですから、試合中では発言者が特定できれば十分であると考えることができます。
以上二点の要求を満たすためには、(信憑性その他の問題を除けば)証拠資料の引用に際しては著者名と発表年を述べるだけで足りるということができます。著者名だけでなく発表年が必要だと考えるのは、しばしば同一の人物による同一の内容が複数の資料に収録されている場合があるという、指示性に基づく要求と、発言者の時間による属性変化18)を考えた上で、発言者の特定をより確実にするための要求に基づきます19)。
もっとも、こうした「最小限の」引用方法は、求められた際に適切に出典を提示できることを前提としています。その意味で、本節(1)で述べたような詳細な出典のない資料については、再現可能性の原則を満たさないものとして、証拠資料としての価値を認めない余地があります。これについては、違法な証拠資料について検討する中で論じることにしましょう(2.3を参照)。
2.2 証明力
§1 証拠資料の評価
証拠内容尊重の原則でも述べたとおり、証拠資料はその内容そのものが評価されます。そして、その評価の結果受け入れられた内容が、その試合における前提として組み込まれ、判断材料として用いられるのです。この節では、証拠資料の評価がどのようになされるべきか、考察していきます。
一般に証拠資料の引用は、ある主張を支持するものとして行われます。そこでは、その証拠資料がサポートしたい主張をジャッジに受け入れさせることができるかどうかが最大の関心事です。証拠資料の効果として主要なものもここにあるといってよいでしょう20)。そこで、当該資料が主張をどの程度支持しているか、すなわちその証拠資料の証明力がどの程度であるかが問題となります。この証明力は3つの要素に整理することができます。
一つ目の要素は、その証拠資料がどの程度信用できるものかという、信憑性の問題です。例えば、「エコ製品を買いたいと答えた人が60%いた」という証拠資料について、エコ製品について調査した人数の母数がどの程度かという問題があります。無作為に抽出した1万人であれば信憑性は高いといえますが、環境セミナーの参加者20人に聞いただけというのであれば、その資料の信憑性は乏しいといわざるをえません。もっとも、評価に際しては常に同じような基準が適用されるわけではなく、統計資料についても、常に人数の多い方が勝つというわけではありません(反例を示す意味での証拠であれば、たった一例でも重要な意味を持ちうる)。従って、この点は証拠資料の性質や証明したい主題との関係を踏まえて判断されなければなりません
二つ目の要素は、証拠資料の内容についての評価です。証拠内容尊重の原則からも、証拠資料の価値はその形式面ではなく、実質面で判断されます。ですから、主張を支持する根拠が伴わない証拠資料は、基本的には単なる主張としての価値しか持ちえないということになります。ただし、これには例外があります。詳しくは、信憑性について説明する部分の後半で論じます。なお、証拠内容の実質的評価については、一般の議論評価と同様の問題ですから、本稿では取り上げないことにします。
三つ目の要素は、主張と証拠資料の間にどのような合理的関連性があるかということです。これは、証拠資料の内容がどのようにして主張を支持しているのかという問題に帰着されます。先の例であれば、エコ製品に関するアンケートの結果が、「日本では環境意識が高い」という主張をどの程度支えるものであるのかということが問題とされるようなものです。
このように、証拠資料の証明力を考える際には、その資料の信憑性と、それを前提として証拠の内容と主張との合理的関連性が要件として挙げられます。以降では、このそれぞれについて検討していくことにします。
ただし、上で挙げた証明力の要素は、証拠資料それぞれについていえる、単独での証明力に過ぎません。議論を評価する際には、個々の論点だけではなく、議論全体での評価がなされます。つまり、シナリオ全体に対する信憑性(scenario credibility)が問題にされるのです。この見地からは、個々の証拠資料に証明力があっても、全体としては証明力が減じられるという場合があります。例えば、全ての証拠資料が同一の出典によるものであるなどの場合ですが、これについてはジャッジの評価に関するところで論じることにします(4.2を参照)。
§2 信憑性
最初に、証拠資料そのものの信憑性について説明します。いかに内容が優れていても、その出典が信用できないという場合は、証拠資料として信用することは難しくなります。ここからも分かるように、信憑性の問題は違法証拠資料の問題と密接に関係します。しかし、ここでは適法な証拠資料についての信憑性を見ていくことにします。
資料の信憑性は、資料の媒体・性質や著者の権威性、そして発行年などの要素によって決定されます。ただし、その信憑性がどの程度証拠資料の証明力に影響するかは、その証拠資料で証明しようとしている事実によって異なります。この点を踏まえて、信憑性を評価するにあたって重要となる各要素について見ていくことにしましょう。
資料の媒体については、その証拠資料が公にされ、一定の責任を負っているかを判断する要素として信憑性に影響します。公刊されている新聞や書籍・雑誌であれば、不特定多数に向けて公開され、社会的な評価を受ける(誤りである場合には批判を受けうる)こと、また一旦公開した後での撤回が困難であることからも、証拠資料としての内容が社会的に担保されていると考えることができます。この点で、インターネット資料は出典の捏造が容易であり、批判を受けた際にすぐ撤回することが可能であることから、信憑性の評価にはマイナスの影響を与えます。しかし、政府や公的研究機関などのサイトは、書籍などと同様に社会的な責任を負っており、簡単に意見を翻すことは難しいですから、こうしたサイトに関して信憑性を下げる必要はないでしょう。
資料の性質は、それがどのような調査に基づくものかという点で、信憑性に影響します。ここには、主に統計資料などで問題となる、規模や調査対象などの問題が含まれます。これについては、統計学の見地から、適正な規模や適切なサンプリングに基づく調査がなされているかなどが問題となります。
著者の権威性は、内容の専門性と対応して、内容の真実性を保証するものとして信憑性に影響を与えるとともに、社会的責任という見地からもその信憑性を高めます。もっとも、資料の権威性を判断するにあたっては、単に権威性があるというだけでなく、資料の内容を根拠づけるものとしての権威である必要があるのはいうまでもありません。また、著者に強い思想的偏りや特定の利害関係がある場合などは、内容によっては信憑性を下げる要因となります。これは、汚職が疑われている政治家が「やっていない」と主張していたとき、発言の信憑性は低いと感じられるような場合と同様です。
なお、証拠資料の証明力の評価に関して、根拠の挙げられない証拠資料を評価しうるかという問題があり、この論点が上述した信憑性の要件に関係するため、ここで説明します。証拠資料には根拠が伴わねばならないというのは既に述べたとおりですが、証拠資料が主張以上の理由を付け加えていない場合であっても、証拠資料の権威性がそのまま根拠として評価できる場合もあります。
例えば、理由が示されていないにせよ、経済アナリストが「来年には景気は上向くだろう」という場合、確信とまではいえないにせよ、一般市民はある程度の期待感を持ちます。その程度で、理由を含まない証拠資料も証明力が皆無ということはできません。そもそも、常に根拠を要求するとすれば、専門的な論点や科学技術に関する議論について、十分な根拠付けのある資料を提出することは非常に困難になります(原発事故のメカニズムについて専門的見地から厳密に説明する場合を想像してみてください)。
ですから、証拠資料の根拠については、主張の性質から、根拠付けを必要とする程度で求められると考えるべきです。もちろん、こう考えることによっても、根拠付けが深ければ深いほど証明力は高くなるということに変わりはありません。
一方で、根拠が伴わない証拠資料の証明力を認めない、すなわち権威性による証明を認めないという見解も有力に主張されています。この立場からは、主張と同内容の文面しかない、いわゆる「一行エビ」は評価できないということになります。この立場は、証拠内容尊重の原則からは一貫しており、また根拠を省略した安易な引用を戒めるという点で、教育的であると評価することもできます。しかし、先ほど述べたように、筆者はこのような見解を支持しません。その理由としては、証拠資料の評価は文面のみならず、その背景にある著者の権威性や発行形式なども含むということが挙げられます。前述のとおり、証拠資料の権威性は信憑性に大きく関わります。そして、たとえ一行エビであったとしても、その信憑性が極めて高い場合、そこで述べられた内容は正しいと推定することは許されるというべきです(逆に、ディベーターが証明を伴わずに行った主張が評価されないのは、その発言の信憑性が乏しいからだということができます)。
ただし、権威性による証明が許されるかは、証明しようとする内容によるでしょう。まず求められるのは、権威の属性と証明対象が一致することです。さらに、証明対象が専門性を有し、権威による証明を必要とするかどうかも判断材料となるでしょう。これは、ディベートにおいて証拠資料を用いるのは、証拠資料を用いなければ判断できない事項があるからであり、そうでなくても判断しうる内容であれば、ジャッジが判断すべきというべきだからです。このような基準によれば、例えば「○×大学工学部教授の資料より『原子力発電所は震度7までの地震しか耐えられない』」というような内容は、ある程度の証明力を認めてもよいことになるでしょう。一方で「△□大学哲学博士の著書より『自由の喪失は死より重い』」といったところで、価値に関する議論は専門知識を有さないジャッジによっても評価可能なものですから、根拠がない限り、哲学の専門家たる権威性をもってして証明をなしたということは妥当ではないでしょう。
このように考えることは、権威性の証明を否定する立場からは「理性的議論を要求するディベートでは妥当でない」という批判がありそうですが、ディベートで行われる議論が一般社会におけるそれと別世界であるかのように捉えることはむしろ不自然であり(先に述べた経済アナリストの例を思い出してください)、我々は普段合理的意思決定の中で権威性を有する情報をも判断材料としている(ディベートのモデルたる裁判や議会でもそうです)という再反論を加えることができます。また、権威性による証明は完全なものではないので、根拠が伴わないことによる証明の弱さは否定できません。この意味で、権威性による証明を認めても、一行エビが横行するといった教育的弊害はないということができるでしょう。
また、証拠資料の権威性に関連して、ディベーターが自らの研究結果を試合中に引用することが許されるかという問題があります。ディベートにおいては競技者の権威性と議論の内容は切り離されるという原則を破らない範囲であれば、その証拠資料が公刊され、客観的に権威性を付与されたものである以上、それを受け付けない理由はないといえます。この場合は、証拠資料の著者である人物と試合で発言している人物は、別の人間であると考えます。ですから、「対戦相手が自分の発行した証拠資料を誤用している」という反論がなされたとしても、そこに実体的な理由が伴っていない場合は、採用することはできないということになります21)。
発行年は、当該文面が現在でも同様の内容を支持しうるものであるかを判断する材料として、証拠資料の信憑性を基礎付けるものです。ただし、この要素は証明する内容によって大きく変動します。時代に関係なく通用する思想や価値規範については、発行年はあまり重要な意味を持ちません。これに対して、ある時点における事実の証明や科学技術のような常に見解が更新されていく分野の証明については、発行年が重要な意味をもつことになります。
ここで問題となるのは、同一の著者について発行年が異なる証拠資料が提出され、その内容に違いがある場合、どのように評価すればよいかということです。普通に考えれば、新しい資料を優先すべきということになりそうです。特に、先に述べたような、発行年が意味を持つ内容に関してはこれが妥当するでしょう。しかし、事実ではなく著者の見解が変化したに過ぎない場合は、発行年が古いほうの見解をただちに誤りとすることは行き過ぎだと思われます。なぜなら、著者の改説が客観的に正しいということが常に言えるわけではありませんし、証拠内容尊重の原則からいえば、古いほうの資料であっても、内容に説得力があればそちらを採用すべきということになります。ですから、同一著者による異なる見解の処理については、発行年はあくまで一要素であり、内容変更の実質的意味を踏まえて扱われるべきだと考えられます。
以上のような要素を総合して、証拠資料の信憑性が判断されることになります。ただし、実務上は、極端な場合を除けば、証拠資料の信憑性について特別な評価がなされることはありません。ほとんどの場合は、議論に即した競技者の主張・攻撃によって初めて、証拠資料の信憑性が問題とされることになります。
§3 主張と証拠資料の関係
証拠資料に信憑性があれば、とりあえずその資料の内容は受け入れることができるということになります。次の問題は、その証拠資料の内容が本当に主張を支持できているのかということです。もっとも、これは論点と証拠資料の対応という狭い意味付けに過ぎません。証拠資料の役割を試合における前提の補充と考える本稿の立場からは、証拠資料が試合の中でどういった意味をもつのかということが問題とされます。
ただし、広い意味での関係性を考える際にも、具体的に提示された論点と証拠資料を考えることは必要不可欠です。ここでは、論点と証拠資料の対応が証明力に与える影響について考えることにします。
主張と証拠資料の関係に関係性がない場合は、証拠資料が伴っているにも関わらず、主張はそれによる証明を与えられていない(正当化されていない)ということになります。この関係性は、証拠内容尊重の原則から、ジャッジが聞いた第一印象の段階からある程度積極的に評価されることになります。ここで判断される関係性の強さは相対的なものになります。ですから、その資料の内容によって主張の真実性にかなり高い確証が得られるという場合から、資料の内容と主張に関連性がないため評価できないという場合まで、評価に幅が生じることになります。
主張と証拠資料の関係という観点からも、証拠資料がほとんど主張の繰り返しであり、何らの根拠も付け加えていない場合の評価が問題となります。このような場合は、主張と資料内容は完全に一致しているため、関係性の観点からは高い評価を受けることとなります。しかし、関連性の要件はあくまで根拠と主張の関係について求められるのであって、主張の同語反復に過ぎない場合は、主張の支持に失敗しているということができます。証拠内容尊重の原則から、証拠資料は文面そのものではなくそこに含まれる意味をも含めて証拠資料を評価する必要がありますから、ジャッジが証拠資料の中に主張を支持する根拠付けを見出せなかった場合は、その資料が無内容であるといわざるをえないからです。
ですから、既に述べたとおり、証拠資料に主張を支持する根拠がない場合は、適切な権威性によって根拠の存在を推定してもよいと考えられる場合を除いて、関連性の要件の強さをもって証明力を肯定することはできません。
もう一つの問題として、証拠資料が事実の提示にとどまり、聞き手の解釈なしには主張の支持につながらない場合が挙げられます。これは全ての資料に多かれ少なかれ存在する問題です。
例えば、「日本の景気は今後よくなる」という主張を支える証拠資料として「企業の設備投資が増加傾向にある」という統計資料が示されたとします。ここで、そのまま評価すれば「企業の設備投資が増えている」ということだけが証明されたということになりますが、聞き手が「設備投資の増加は景気の拡大局面によくみられる」といった前提(これが試合中に適用できる範囲の知識かどうかは別の問題です)を用いて解釈すれば、主張はある程度支持されたと考えることができます。しかし、スピーチでの言及なしにそうした解釈が許されるのか、恣意的な介入に当たらないのかという疑問が生じます。もしそうした聞き手側の解釈を完全に認めない場合は、程度の差はあれども証拠資料の内容と主張の間には差がある以上、およそ全ての証拠資料は採用不能になってしまうという妥当でない結果になってしまいます。
ですから、行き過ぎでない限りは、聞き手側の補充的な解釈が認められるべきだといえます。ただし、その解釈程度については、一般人であれば容易に想起できるつながりであるというように、一見明白に主張を支持していると考えられる程度に制限されなければなりません。
このように、証拠資料と主張の内容があまりに飛躍している場合には証明力はないと評価されますし、一般的に関係性が小さいと考えられる場合は、証明力の点でも小さく評価されることとなります。しかし、そのような場合であっても、ディベーターが主張と資料の間の因果関係を口頭で説明する場合は、その説明になお証明の必要性がある場合を除いて、主張と証拠資料の間に合理的関連性を肯定する余地があります。
2.3 違法な証拠資料
§1 改竄・捏造された資料
違法証拠排除の原則について説明したとおり、違法な証拠資料とは、原典の意味を歪曲させた資料のことです。そのような資料は、判定を不当に誤らせることから、競技上あってはならないものです。その中でも、資料の改竄や捏造は、原典には存在しない文面を作り出すものですから、もっとも重大な違法ということができます。このような行為は故意でしかありえないものであって、競技者として決して行ってはならない重大な反則行為だということができます(スポーツでいうドーピングよりずっと悪質です)。ですから、当該試合のみならず、その大会の出場資格を剥奪されるレベルで罰せられるべきです。
資料の捏造は、全く存在しない証拠資料を作りだす行為を指します。資料の改竄とは、実際に存在する証拠資料の文面を変える行為と、その出典の改変を指します。証明力の部分で説明したように、資料の出典は資料の内容とともに証拠資料の証明力を左右する要素であり、その改変は証拠資料の評価を変動させるからです。
§2 不適切な引用
不適切な引用とは、出典を著しく欠いた証拠資料や、証拠資料の原典の趣旨を没却あるいは歪曲するような引用がなされたものを指します。具体的には、恣意的な中略が問題となります。
証拠資料の引用においては、証拠内容尊重の原則の延長から、単なる文面上の意味にとどまらず、原典の趣旨を尊重する形での引用がなされるべきです。この理解からは、単に文面上そのような内容が書かれていたとしても、文脈として原著者がそうした内容を表現する意図を欠いていた場合には、それを証拠資料として採用するべきではないということになります。ですから、証拠資料の一部分を恣意的に切り出し、原典の内容を歪曲するような引用については、証拠能力を肯定することはできません。
例えば「日本の自衛隊イラク派遣は確かに現地の生活を向上させた一面を持つが、それによって現地のテロ勢力を刺激し、地域の安定を害したという側面も否定できない」という内容の文面について「日本の自衛隊イラク派遣は確かに現地の生活を向上させた」という部分だけを引用することは、意味の歪曲がなされているとして、証拠能力が否定されます。
基本的には、文面の意味は文章単位で構成されるものであるから、句点以外によって引用を終わることは認められません(引用の始点も文頭であるべきです)。また、中略については、中略したことが明示される限りで認められますが、全体として意味を歪曲するような中略が許されないことはいうまでもありません。また、意味的に問題がないとしても、あまりに長い中略は、原典の再構成にあたると考えられますから、不適切な引用といえます。中略と称して前後関係を逆転させた引用を行うことも同様です。
ここで問題となるのは、ある主題について特定の見解を有する筆者の文章から、その見解に反する内容の文章を取ってきてよいかということです。具体的にいえば、いくつかの見解を検討した上で結論を出しているという形式の文章から、後で筆者によって批判されるところの見解に関しての説明を引用することが許されるか否かが問題となります。
これについては、原典の意図の尊重を貫くとすれば、筆者が最終的に否定するところの内容は引用できないということになりそうに思えます。しかし、これでは使用できる証拠資料の範囲があまりにも狭くなってしまいますし、そもそも証拠資料の文面と著者の思想が同一でなければならないと考える必然性はありません22)。ですから、論旨の一部分として成立している文章については、筆者の最終的結論に反している場合でも、適切な方法で引用してよいと考えてよいでしょう。証拠資料として提示される文面は、著者の思想によってではなく著者の権威性や分析自体によって支持されるものですから、こうした見解をとることに問題はありません。
また、文面中の括弧書きについて、中略を行ってよいかという問題もあります。例としては、「2005年の政府開発援助(ODA)は…」という文章における『(ODA)』の部分まできちんと読む必要があるかということが挙げられます。
もちろん、引用に際しては原典にある文章の全てを再現することが原則です。しかし、証拠内容尊重の原則を実質的に解釈するならば、意味の同一性は文面が同一であることを意味するのではありませんから、意味を変えない程度であれば省略を施してもよいと考えられます。括弧書きで表記されているということは、その部分が補足的なものであると考えることができますので、そうした部分を引用の際に省略することは可能と考えてよいでしょう。また、これを中略としてスピーチ中に明示する必要も無いでしょう(上の例でいうなら、括弧書きの部分を引用するのはかえって不自然でもあります)。
ただし、括弧書きであっても、本文の内容を根拠づけるデータが含まれるなど、本文とは独立に意味を有する内容については、省略を許すべきではありません。そのような省略は相手に対して批判の機会を与えないことにもなりますから、事実上の意味歪曲として評価されることになります。
§3 不適切な引用
違法な証拠資料が発見された際には、ジャッジはその職権により当該資料の評価を下げ、あるいは評価しないことができます。また、このような処分を検討するために、ジャッジは職権によって証拠資料の提示を請求し、証拠調べを行うことができます(4.1参照)。
ここで、相手側が同意した違法証拠資料の評価に関する問題があります。違法証拠資料の内容が実は相手方に有利なものであるとすれば、相手が同意する限りにおいて判断材料から排除しないことが、違法行為を行われた相手側への配慮であり、かつ、違法行為に対するペナルティになるという考え方もありうるでしょう。このように考えれば、たとえ不適切な証拠資料があったとしても、相手の同意23)があればその資料は当該試合では違法とみなさないことが許されることになります。
しかし、このような考え方は違法行為に対する倫理的制裁や、違法行為の抑止という観点からは正当化されうるものの、違法証拠排除の原則を支える実質的理由として誤った前提を試合に持ち込むことが許されないということがあり、またそれによってジャッジングの廉潔性を保たなければならないという要求を考えると、やはり相手方の同意の有無に関わらず、排除すべき違法行為は全て排除すべきだということになるでしょう。相手方が同意をなすことによって証拠資料の違法が治癒するわけではないので、このような結論を取った結果、違法行為の相手側が損をすることになるとしても、仕方のないことです。
さて、以上の議論は違法証拠資料の存在が判明したときのことを前提としていますが、実際には違法行為は簡単に分かるものではありません。それだけに、ディベーターの違法証拠資料使用の欲求がなくなるということを期待するのは難しいのかもしれません。捏造や改変ということはまず考えられませんが、英語のディベートにおいては訳出の際に(ほとんどが過失でしょうが)不適切な訳による意味の改変が起こっているそうですし、日本語のディベートでも、句読点を尊重しない引用といった軽微な違法使用が普通に行われている場合は少なくないように思います。
それにもかかわらず、現在のところは、幸いにも深刻な問題はほとんど起こっていないと評価することができます。これは競技者の倫理意識の高さによるものでしょうが、違法証拠資料のチェック体制の構築については、別途検討がなされる必要があるでしょう24)。
なお、違法の程度が悪質であった場合に、それを投票理由にして当該チームを敗戦にすることが可能であることは、すでに述べたとおりです。
第3章 試合における証拠資料の使用法
3.1 証拠資料の引用
§1 引用の要件
証拠資料は、引用という形で提示されなければなりません。これは、証拠資料が試合に新たな前提を持ち込むものであることから説明することができます。証拠資料を客観的なものとして提示するためには、試合の外で収集した議論であることを明示する必要があるということなのです。
ここで問題となるのは、引用の形式です。引用が正しくなされたとされるためには、その方法が適切でなければなりません。証拠資料が正しく引用されなかった場合は、証拠資料を新しい前提として認めるための要件を欠くため、その資料を採用することはできません。先に論じた試合において要求される出典の要件も、その多くは、試合での引用に際して要求されるという形で問題となります。
引用とは「自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと」(広辞苑)とされます。ここから分かるように、引用として成立するためには、自説そのものではなく、他の文章・研究を引いているということが明示される必要があります。この見地からも、引用先を示すという出典の必要性が生じるのです。出典の要件で論じたとおり、出典によって証拠資料の特定性が確保されることによって、その資料が他の特定の文献から引かれたものであることが保証されることになります。
また、他の文章・研究を引いていることを明示するためには、自分の議論と他から借用した議論の区別を明らかにすることも必要です。これがなされることにおいて初めて、ジャッジは引用された部分を証拠資料として認識することができるのです。つまり、ジャッジとしては、引用部分の明示がなされなければ、証拠資料として評価する内容を確定できないので、そのような引用は評価することができないのです。また、対戦相手にとっても、証拠資料が述べる範囲が確定されなければ、攻撃・防御の対象を明確に定めることができません。よって、引用の際にはどこからどこまでが資料の対象であるかを明示しなければならないのです。なお、引用部分の特定・明示は学術論文における引用作法の基本でもあります。
引用範囲の特定・明示は、一般的には「〜より引用開始…引用終了」という形でなされます。これが最も厳格で望ましいのですが、他方で、こうした引用方法は口頭のスピーチにおいて必ずしも自然であるわけではなく、より簡潔な方法で示すことも可能であり、また望ましいといえるかもしれません。例えば、より自然な明示方法としては「〜という資料にはこうあります。…終わり」というような方式が考えられます。
引用の合図に関していえば、引用とされる範囲が特定されればよいのですから、その要件さえ満たせば、それをどのように明示するかは競技者に委ねられていると考えることができます。この見地からは、必ずしも引用部分を明示する言葉が伴わなければならないわけではないということもできます。例えば、主張と証拠資料のみで構成される立論においては(望ましくはありませんが)形式上の区切りを認識できるため、引用終了の言葉を省略することも可能でしょう。
ただし、適切な間を空けるなど、引用が終了していることを容易に認識できる必要があります。認識が困難である、明らかでないといった場合は、引用部分の特定が十分なされていないというべきです。
§2 不適切な引用の扱い
以上のように、証拠資料は適切な方法で引用される必要があります。それでは、引用が不適切であった場合には、その証拠資料はどのように評価されるのでしょうか。
引用に際して要求される出典(これについては2章1節で論じました)が示されなかった場合は、その資料が特定の文献から引かれたものであることが不明確であることから、適切な引用ということはできません。試合中に示されるべき出典の要件が満たされなかった場合は、それを証拠資料として認識することは難しいので、端的にその証明力が否定されるとすべきでしょう。試合中に示されるべき出典の要件は特定に必要な最小限度のものですから、それすらも示すことができない以上は、もはや有効な資料を提示しているとみなすべきではありません。
それでは、証拠資料の引用範囲が不明確である場合はどうでしょうか。すでに述べたとおり、引用範囲の確定について、引用者に引用範囲を示す義務があるのは明らかです。そうであれば、基本的には証拠資料である範囲が不明確である場合は、相手チームに有利となるように解釈がなされるべきです。よって、証拠資料であることが疑わしい文面については、引用がなされていないと考え、証明のないスピーチに過ぎないと考えるべきです。これより、引用されているかどうか不明確な部分については、証拠資料としての証明力を否定することになり、せいぜい客観的論証を伴わないディベーターの見解としての価値しかもたないということになります。
ただし、一般的に考えて証拠資料の引用だと見なせるような場合は、疑いがあるからといって直ちに引用を否定することは、あまりに硬直的にすぎます。例えば、うっかり引用終了の宣言を忘れたが、話の切れ目からそこまでで引用が終わったことが明らかであり、相手チームもそのことを認識しているという場合です。この場合、確かに競技者に非はあるとはいえ、引用に失敗した証拠資料が他の点において違法でないのならば、対戦相手の攻撃・防御を不当に妨害しない限りで評価に入れてもよいでしょう。また、引用部分の特定・明示が疑わしい場合は、ジャッジには職権による証拠調べの機会が保証されています(4章1節で説明します)し、対戦相手には質疑における確認の機会があります25)。もちろん、これらの機会を行使するのはディベーターやジャッジの意思によるものであり、相手のミスに対して確認を行う義務があるとまでいうことはできないのですが、軽微なミスに対しては、確認できたにもかかわらずそれを怠って引用部分の制限を行うのはかえって妥当性を欠くともいえます。
しかし、上の例のような軽微なミスではなく、スピーチが速すぎて証拠資料の範囲が分からないといった不備の場合には、不適切な引用に対して厳しい態度で臨むことについても一定の合理性があります。その場合は、疑わしい部分は証拠資料として認めないことになります。それでは、そのような場合においてもジャッジやディベーターが資料の確認によって引用範囲の確定を行い、本来不明確であった証拠資料の範囲を確定させることで一定の効力を認めようとする行為は認められるのでしょうか。
本来きちんと読まれていれば証拠資料として評価できたということが推定される場合には、ジャッジがその職権によって証拠資料の範囲確定を図ることによって判断材料が増えるという利益があり、それによって妥当な判定に近づく可能性があるので、ジャッジとしては積極的に資料の確認を行う動機があります。しかし一方で、それは相手側を不当に利する場合もありますので、証拠資料の範囲を確定しないと試合に混乱が生じると思われる場合など、正当な理由がある場合に限られるでしょう。そのような理由がない場合は、ジャッジが証拠調べによって引用範囲を確認する行為は、不当な介入とみなされる余地があります。
それでは、そのような不当さをディベーターが主張し、資料確認を中止させることが可能だといえるでしょうか。不適切な引用をした側が不当介入を主張できないのは当然のこととしてよいでしょうが、対戦相手にとっては、証拠資料の範囲確定によって証拠資料の証明力が発生し、不利に働く可能性がありますから、そのようなジャッジの証拠調べを、不当に一方当事者を救済し、その議論を利する行為として弾劾する権利があると考えることができそうです。
しかし、この場合においても、以下三点の理由から、ディベーターは「不当な介入である」と主張してジャッジの証拠調べに対抗することはできないとするべきでしょう。
一点目の理由として、ジャッジにはその試合で提出された議論を自由心証によって決する権限があります。ですから、極端な場合を除けば、ジャッジは不適切な証拠資料の引用についても心証によって一定の評価を与えることができます(例えば、一定の引用範囲特定がなされたと推定するなど)。そうであれば、ジャッジの証拠調べがなくても恣意的な介入はあり得るわけで、証拠調べによって当該証拠資料の範囲が確定され、それを前提として試合において議論を行ったほうが、公平な議論に資すると考えられます。
二点目の理由として、ジャッジにはその試合において真実公正な評価を行う義務とそのための職権を有しています。そのような見地から証拠調べが正当化される以上、競技者の抗議に対抗することができます。
三点目の理由として、引用範囲が不明確であるとしても、証拠調べによって判明した限りの引用範囲については、実際に引用されたものであるということができますから、証拠調べの結果を反映させることに問題はありません。
以上の理由から、ジャッジは常に証拠調べによって証拠資料の範囲を確定することができます。しかし、証拠資料が読まれたかどうかも分からないのに証拠調べを要求することは不自然であり、行き過ぎであるとは思います(実際にはそのようなことはないでしょうが)。
一方、引用された側のディベーターによって質疑などの機会で証拠範囲の確認がなされた場合は、ジャッジはその結果を尊重すべきです。質疑によって証拠範囲を確認した時点で、そのチームは不適切な証拠資料の引用を正すことによって自らが被る不利益を容認していると考えることができますし、これを容れないことは競技者の意思に反することになります。ただし、質疑における証拠範囲の確認が適切に行われなかった場合は、ジャッジはその結果を評価しないこともできるし、改めて職権による証拠調べを行うことも可能です。また、相手側の確認に類するものとして、相手側からジャッジに証拠調べによる引用範囲の確定を請求された場合は、ジャッジは特別な理由がない限りは請求を受けて証拠調べを行うべきでしょう。
最後に、引用者が当該スピーチの終了後に自ら証拠範囲の確定を求める場合を考えます。結論としては、このような行為は許されません。不適切な引用をなした競技者にそのような権限は存しないからです26)。また、自チームのスピーチ中に引用範囲に関する釈明を行うことも許されません。不適切な引用を有効にするためには、適切な引用として再度証拠資料を引用するべきであり、そのような手続きを経ずに引用範囲の指定をもって証拠資料の引用範囲確定を認めることは、証明力のない議論に対して新たに証明力を発生させることですから、新出議論を認めることと同様の行為です27)。よって、立論が1回しかないディベート甲子園のようなフォーマットでは、証拠範囲の確定を欠いた引用について、スピーチ中に引用者側から訂正を行うことは事実上不可能だといえます。
§3 質疑における資料の引用
本節の締めくくりとして、引用に関する問題の応用である、質疑のステージにおける証拠資料の引用が許されるのかという問題を取り上げます。上で触れた質疑における証拠資料の引用範囲確定という場面は、立論で提出された証拠資料に関する議論でした。それでは、質疑において新たに証拠資料を引用することは許されるのでしょうか?
ここで、質疑の意義付けについて確認しておきましょう。質疑のステージでは、立論で述べられた事項に関する確認を目的とした相手側からの尋問がなされます。応答側には黙秘権が認められず、誠実に回答することが要求されています28)。質疑で述べられた議論の扱いについては諸説ありますが、質疑は立論で提出された議論の補足であるというのが一般的な見解といえます(例えば、ディベート甲子園のルールではそのように明記されています)。
しかし、ディベートにおける質疑の目的としては、議論内容の確認として相手に立論を補足させることに加えて、立論で提出された議論を弾劾することによってジャッジの立論に対する心証を揺らがせるという点を無視することはできません。そうであれば、たとえ反駁において言及がなされないにせよ、立論の評価に質疑の内容を反映させることは可能であると解するべきです。
こう考えることは、質疑を立論の補足と捉え、反駁の場で再度言及することを要求する見解と何ら矛盾しません。なぜなら、ジャッジは試合で述べられた全ての議論について(公平性・合理性の要求を超えない範囲で)自由に評価することができますから、質疑の内容を立論段階で得られた心証の補足として評価に反映させることはジャッジの自由であると考えられるからです29)。さらに、質疑においては尋問側が立論の内容に対抗して論拠を述べることや応答側が新たな論点を追加することは許されないのですから、上記のように「反駁で言及されない尋問内容」を判定材料に加えたところで、立論の補足の範囲を越えるものではない(新しい論点を構成するものではない)ということができます。
以上の見解からは、質疑の場は、立論で明らかにされなかった事項の確認及び立論内容の弾劾をなす反対尋問の場として理解されることとなります。事項の確認については、質疑を反駁による言及を要する立論の補足と解する立場によっても、当然に記録され判定に考慮される内容です。しかし、ルールの文言及び質疑の趣旨を実質的に捉える先ほどの立場からは、立論内容の弾劾についても、ジャッジの心証形成の一材料として独立に評価を受けることとなります。もちろん、質疑における議論が独立に新たな論点を構成することはないことはいうまでもありません。
証拠資料の論点から話が脇道にそれましたが、このような質疑ステージの性質を理解することによってはじめて、質疑における証拠資料の扱いについて正確に考えることができます。以上の前提から、質疑における証拠資料の引用について考えていきましょう。
前述の理解によっても、質疑において尋問側が証拠資料を引用することは許されません。なぜなら、証拠資料は新たな根拠の提示という側面をもっているため、それを引用することは、立論内容の弾劾を越えた独立論点の提示による反証を行っていることになるからです。質疑で立論を弾劾するという場合、その意味はあくまで立論で述べられた論拠の薄弱さを指摘するということにとどまるのであって、立論の論拠を否定する論拠を持ち出すことは含まないのです。逆に言えば、立論で読まれた証拠資料の証明力を否定するための質疑は許され、またそれは再度言及されなくてもジャッジの判定に採用されうることになります。
問題となるのは、応答者による資料の引用です。反対尋問としての質疑の理解を裏返せば、応答の役割は、立論の信憑性を保持することといえます。ですから、質疑の場で応答者が主張できるのは立論で述べられた議論に関連する内容のみであり、新たに独立の論点を構成して立論を補強することは許されません。よって、尋問者と同様、原則として証拠資料の引用は認められません。
ただし、応答者が証拠資料を引用してよいと考えられる例外的な場合があります。
その一つとして、証拠資料の引用が立論の純然たる補足として扱われる状況が考えられます。これは、尋問者による弾劾によって被害を受けた議論を回復するため、立論で述べたものと同様の証拠資料を提示する場合です(回復証拠の提示)。例えば、一例に過ぎないのではないかといった弾劾的質問に対して、同じような別の例を提示するという場合です。もっとも、尋問者には質疑の管理権がありますから、質疑者に認められていない引用(勝手に読み出すという場合)は、応答者の立場を逸脱した不当な引用として、その証拠資料の引用は評価することができません。また、相手の尋問に対応せず、立論を強化する証拠資料を提示する行為(増強証拠の提示)は、たとえそれが立論で提示した証拠資料と同内容であっても、許されないと解すべきです。
証拠資料の引用が許されるもうひとつの状況は、質疑者が進んで証拠資料の引用を促す場合です。この場合は、質疑者が弾劾のため必要と考えている(と推認される)こと、新たに根拠を述べることを許すことによって自己に不利益な応答を許容していることから、応答者に証拠資料の引用を許しても、公平性その他の面で問題はありません。ただし、この場合によっても、完全に独立の論点を構成するような、質疑の趣旨を逸脱した証拠資料の引用は認めるべきではありません。なぜなら、質疑のステージはその形式からも、新しい論点を提示する場として想定されてないからです。
また、質疑者が引用の中断を申し出た場合は、応答者は速やかにこれに応じる義務を有し、これに反する引用は評価することができません。もっとも、一度引用を促した質疑者には、その引用がことさらに質疑を遅延させるものでない限りは、信義則上最後まで引用を許すべきだということもできるでしょう。
なお、以上のような例外的引用においても、通常のスピーチ同様、適切な出典と引用部分の明示は当然に要求されることはいうまでもありません。
3.2 資料の請求・提示
§1 資料提示の請求
競技者は、自己の準備時間において、相手チームに対して証拠資料の提示を請求することができます。この制度の趣旨は、反論の準備として対戦相手の提示した証拠資料を綿密に確認する機会を与えることで、より的確な反駁を行わせるというところにあります。
前に述べたように、証拠資料の提示を試合の前提の補充と捉え、証拠資料の内容は当該試合において一般常識とともに判断材料として加えられるという見解からは、その試合においた共有された前提である証拠資料は常に確認することが可能だといえます。その意味で、相手から提出された証拠資料を吟味するこの制度は、前提として組み込まれた内容を確認することで、競技者の反論準備権を保障するものとして考えることができます。もっとも、証拠資料は提出した側が自分たちの利益のために所有し使用するものであるという側面もありますから、常にその内容を確認できるとするのでは使用者に不便が生じる恐れがあるため、確認の機会を自分たちの準備時間に限るという制限が加えられます。
ここで、ディベートでは相手の議論を聞き取ることが求められているのであるから、文章によって議論の内容を確認することは許されないのではないかという疑問があるかもしれません。しかし、ディベートにおいて、聞き取れた範囲でしか議論をしてはならないという規律があるわけではない30)ので、証拠資料提示請求のように、視覚によって議論を吟味する制度も存在を許されます。
なお、このような制度についても公平性が要求されるのは当然ですから、証拠提示を請求できるのは自チームの準備時間のみであり、準備時間が終われば資料を返還しなければなりません。これによって、資料確認の機会は公平に与えられた準備時間の枠内と等しくなり、公平性の問題が解決されます。
証拠資料の提示は、自チームの準備時間内に与えられた権利ですから、権利を有するチームは試合中に読まれた全ての証拠資料について、時間内であればいつでも提示を請求することができます。ジャッジはこれを制止する権限を持ちませんし、対戦相手もこのような請求を断ることはできません。また、提示を請求できる証拠資料の数には制限がありませんし、求める資料を特定しない概括的な請求についても許されることになります31)。しかし、証拠資料の提示は試合で提示された議論の吟味を目的とするものですから、その試合で読まれなかった証拠資料に対する提示請求は権利の濫用であり、そのような請求は認められないと考えられます(請求された側から拒否できる)。
§2 資料提示請求への対応
それでは、請求に応じたというためには何を提示すればよいのでしょうか。資料提示の趣旨は試合で読まれた証拠資料の内容を吟味することにあるので、提示するときには試合中で引用した文面と同一のものを渡す必要があります。
ここで、議論内容の吟味という要求は前後文脈や中略部分の検討にも及ぶとして、原典もしくはそのコピー、あるいは相当部分を記録した書面を要求しうるとする見解もありうるところです。これについては、出典の真実性を担保して違法証拠を排除するという要求と試合における利便性の比較衡量の結果、妥当な結論を考察する必要があります。現実には、膨大な証拠資料について原典のコピーを全て用意・管理することは著しく困難であり、提示する資料は必ずしも原典またはそのコピーである必要はないと解されているようです。
ここで、このような解釈によって証拠資料の満たすべき原則が損なわれないかということが問題となります。特に、再現可能性の原則との抵触が疑われるところです。
しかし、以上のような運用方法は、再現可能性の原則の趣旨に照らしても妥当だということができます。なぜなら、再現可能性の原則は試合中の再現可能性を要求するものではなく、事後的に証拠資料の存在を確認できれば十分満たされるものであるから、適切な出典が確保される限りにおいて、原典を記録した書面の提示でも許されるべきだからです32)。また、証拠内容尊重の原則についても、試合で議論される証拠資料の証明力に関しては、読まれた証拠資料の文面及び出典によって評価がなされるのですから、試合で提示された証拠資料の記載された書面を提示できれば足りるといえるでしょう。よって、再現可能性の原則による出典の要求によって事後の確認が可能であれば、違法証拠排除の原則についても一定程度満たされていると考えることができます。証拠資料の提示に際しては、引用部分を記載した書面で足りるとしてよいでしょう33)。
ただし、証拠資料の確認はその信憑性に対するチェックという意味合いもあるので、その中には引用時に読み上げる最低限の出典のみならず、再現可能性を満たすための出典も記載されている必要があるというべきです。また、引用時に中略した部分については、提示する際には取消線で表記して中略部分の内容が確認できるようにするなどの配慮が求められるところです。
証拠資料の提示請求を求められた場合は、適切に請求された側としては、速やかにそれに応じる義務があります。請求に応じることができなかった場合や意図的な遅延がなされた場合には、相手チームの反論準備権を損ねたことを理由として、その行為を敗戦理由たる反則行為として捉える余地があります。また、敗戦までには至らないにせよ、提示ができなかった証拠資料の信憑性についてマイナスの評価がなされることは避けられません。
提示請求に対して、引用者は誠実に応対し、速やかに資料を提示すべきことは以上の通りですが、ここで、特定のなされた証拠資料請求に対して、試合で読んだ証拠資料を全て渡すといった行為が許されるかが問題となります。この場合、請求した側が確認したい証拠資料を確認することになるのですが、これは、証拠資料の内容を保障すべき引用側のチームがその責任を相手側に押し付けていると考えることもできます。よって、特定のある請求によって求められた証拠資料以外の書面を大量に渡すことが実質的な遅延行為と評価される場合、提示請求に適切に応じたということは難しいので、反論準備権の侵害として反則行為を構成すると考えるべきでしょう。
第4章 ジャッジの証拠調べ
4.1 ジャッジによる資料請求
§1 資料請求の趣旨
ジャッジは、試合中に読まれた証拠資料について疑義がある場合は、職権によって証拠資料の提示を要求し、証拠調べを行うことができます。本節では、ジャッジによる証拠資料の請求と、それによる証拠調べがなされる目的・趣旨について考察します。それに関連して、ジャッジの証拠調べがどのような範囲で認められるのか、また認められるとして問題はないのかという点について考えていきます。
最初に、ジャッジにこのような職権があることの意味について考えてみましょう。この理解については、ジャッジの任務そのものに対する理解が大きく影響してくるのですが、この点を詳しく議論することは本稿の範囲を越えてしまいます。よって、ここでは「ジャッジの任務は試合で提出された議論を公平性・教育性の見地を交えた上で客観的に判断することである」という通説的見解を基に考察を進めることにします34)。
それでは、そのようなジャッジの任務に鑑み、ジャッジによる資料請求はどのような見地から正当化されうるのでしょうか。これには、主に2点の根拠があります。第一には、違法証拠排除の原則を貫徹し、不当な議論を排除するという目的が挙げられ、ます。第二に、ジャッジの証拠資料に対する誤謬をただし、審査結果の公平性・客観的妥当性を向上させるという目的が挙げられます。
ここで、ジャッジの任務の中に、試合で提示された議論の真実性を探求するというものを挙げる見解からは、第二の理由をより積極的に肯定し、さらに推し進めることで、資料を請求しての証拠調べによって議論の真実性を積極的に判断するということを主張することもできます。しかし、ジャッジの任務に対するこうした理解には疑問があります。すなわち、ジャッジは試合で提示された議論によって得た全心証から公平な判断を下すことこそが任務であり、議論されなかった範囲にまで真実性を考慮する必要はないし、むしろそれは恣意的な介入として厳に戒められるべきなのです。
ディベートでは競技者の主張した議論のみに基づいて判定を下す弁論主義35)がとられているのであって、ジャッジが職権によって判定材料を補充する職権探知主義は採用されていないのです36)。よって、試合記録を補充するために証拠調べがあるという見解を支持することはできません。請求による証拠調べの趣旨は、第一の理由を中心に考えるべきです。
それでは、第一の理由から検討していきます。違法証拠の排除のために最も有効なのは、最終的に違法証拠か否かを決定するジャッジが積極的なチェックを行うことだといえるでしょう。ジャッジによる証拠請求は、職権によって疑義のある証拠資料を調査し、違法証拠の採用を未然に防ぐ効果を持つ、望ましい行為であるということができます。しかし、判定を出す前に全ての資料を調査することは現実的に不可能ですし、既に述べたように、請求によって原典あるいはそのコピーを提出させることを義務付けることはできない以上、完全に違法性を指摘することはできません。さらに、後述するように、スピーチ外による証拠調べが行われることは判定の公平性に影響を与える可能性を有しています。ですから、特に疑いの強い証拠資料にのみチェックがなされれば足りるし、またそうであるべきだということができます。違法証拠排除の目的があるといえども、その探知のための職権行使は控えめであることが求められるのです。
第二の理由である審査精度の向上という点については、ディベートでは議論の欠落や伝達の失敗も含めて判定を行うことが公平性・妥当性の観点から要求されていることを考えると、審査精度が高まればよいということが一概にいえるわけではありません。つまり、ジャッジが理解できなかった議論は、理解できなかったものとして受け取ることが正しいと考えることができます(もちろん、これはジャッジに議論を理解する義務が存在しないということは意味しません)。
しかし、この考えを貫くことは判定に困難を生ぜしめる場合があります。例えば、特定の論点について相反する証拠資料が提出され、他の論点で両者の主張が拮抗しているため、それらの証拠資料の解釈が勝敗に直結するような場合が挙げられます。こうした場合に立証責任を満たしていないとして一律に議論を棄却してしまうことは、判定の内容としては画一的に過ぎ、教育的見地からも疑問があります。このように、判定における当該証拠資料の重要性と、証拠資料の文言に照らし合わせて詳細な検討を行うことの必要性が高い場合は、証拠資料の請求を認める余地があるというべきでしょう。このような事情の下で証拠資料を別途検討することは、均衡した状況の打破という両当事者に中立な動機による審査であること、実際に読まれた内容を精査して試合の内容を客観的に再審査するということから、公平性の観点からも特別な問題は生じないと考えられますから、例外的に証拠資料の請求が許されるのです37)。
まとめると、ジャッジによる証拠資料の請求は、スピーチの全趣旨のみを判定材料にすべきであるという見地から、違法証拠の疑いが強い場合と、当該証拠資料を調査することの必要性が高い場合にのみ認められることとなります。もっとも、ジャッジの証拠調べに対して競技者が対抗することは不可能と思われる(職権によるものであるから)ので、事実上はジャッジの裁量に委ねられることとなります。それだけに、ジャッジには、職権行使に対する自制が求められます。
なお、ジャッジに対して提出すべき証拠資料については、上で述べたように引用部分を記録した書面で足りるといえます。特にジャッジについては、原典の提示は試合で引用されなかった部分を見せることになり、ジャッジの心証を汚染するという弁論主義違反に当たる危険性があるため、原典の提示は例外的に求められる行為だということができます。
§2 試合中の資料請求
試合中のジャッジによる資料請求は、スピーチの進行を妨げる効果を持つので、できるだけ行われないことが望ましいといえます。また、ジャッジが職権による証拠調べを行うこと自体が、当該証拠資料に対するジャッジの疑義を表明することにつながるため、競技者に対して影響を与える可能性もあります。さらに、資格によって証拠資料を精査することは、ジャッジの証拠資料内容に対する理解を深めることとなり、スピーチによらない不当な心証形成につながる恐れもあります。
よって、試合中に資料請求を行うことができるのは、試合後の資料請求では間に合わないといった特別な事情がある場合に限られると解するべきです。例えば、明らかにその証拠資料が違法であると疑われ、試合中に判断を下してその内容を排除しなければ試合に影響を及ぼすという場合などです。この見地からは、審査精度の向上という要求から試合中に資料請求を行うことは認められないことになります。
試合中に資料請求を行うとしても、それはディベーターの準備時間の間になされなければならないことは当然のことです。また、証拠資料は引用者が準備時間中に用いることもあります。この場合は、ジャッジによる証拠調べを行うとしても、ディベーターの資料確認を妨害しないように配慮がなされるべきです。よって、特に強い理由がない場合は、資料を引用したチームの相手方の準備時間に請求を行うよう配慮することが望ましいですし、相手チームが別に資料提示を要求した場合は、そちらを優先させるべきです38)。
試合中に証拠調べを行い、違法性の発見や引用範囲の特定変更があった場合は、その旨を両チームに通知すべきです。その場合、ジャッジが認定した通りの内容が試合に反映されることになります。なお、発見された違法が悪質で敗戦に値するものであった場合は、ジャッジはその場で当該チームの敗戦を宣告することが可能だというべきですが、これについてはジャッジの判定作業が試合後にしか許されていないと見る立場からの異論もありうるところです。
§3 試合後の資料請求
試合後の証拠調べは、試合で出される議論の内容に影響を与えるおそれはないので、試合中の資料請求より要件が緩和されます。しかし、判定までの時間が遅くなるという点では試合の進行を妨げる影響があり、また証拠調べによる一方的な心証形成の可能性は試合中の証拠調べと同じく(あるいはそれ以上に)妥当するので、試合後の場合であっても職権による証拠調べは必要最小限にとどめるべきだといえます。
ここで、試合後の資料請求が判定のプロセスに含まれるのか否かという問題を提起することができます。こう考えることは、試合で提示された議論を知覚し、フローシート及び記憶の中に記録する場面(知覚記録作業)と、記録を基に判定を導き出す場面(判定導出作業)は、概念上異なるものだと考えられるという理解によります。この理解からは、資料請求による資料のチェックが知覚記録作業にあたるのか、判定導出作業にあたるのかという疑問が生じます。この違いは、証拠調べで許される作業の範囲について影響します。
直感的に考えれば、試合で提示された証拠資料の吟味は、知覚による作業にあたるものと考えられます。こうした理解によれば、職権による証拠調べは、試合で提示された議論の記録修正という形で間接的に反映されることとなり、直接に判定の理由とすることはできません。判定精度向上の要求による証拠資料の提示が要求される場合がある以上、判定作業中に資料請求を行うこともありうるところですが、その場合においても、理論上は証拠調べの際には判定作業から脱し、職権による再度の知覚記録作業に入ると解釈すべきです。この結果、フローシートに記録されていなかった内容を証拠調べの結果新たに書き加えるといった行為は、「スピーチ内で記録しなかったことについてスピーチ外で記録する」ということになるため、弁論主義に反して許されないことになります。
ですから、証拠調べの結果得られた証拠内容についての理解は、スピーチ中に認識できた内容の訂正とみなせる範囲内でのみ認められ、聞き取れなかった内容を新たに加えることは認められないことになります。ですから、ジャッジが証拠調べでなしうるのは、記録した内容のうち誤っている部分をフローシートから削除することと、新たな内容の追加とみなされない程度でフローシートを修正することに限られます39)。
このような理解がジャッジング実務に与える影響としては、請求した証拠資料を判定作業の間留めおくことができるかという問題があります。これは、試合後に別室で審査を行う場合に特に顕著に現れる問題です。職権による証拠調べを知覚の作業と解するならば、そこで得た資料はフローシートあるいは記憶の中で記録されて判定材料となるのみであり、提示された資料を判定の際に用いる(書面を参照する)ことは許されないことになります。これは、ディベートの判定において、スピーチの一切を記録した書面による審査が行われるわけではないことからも、容易に理解することができます。資料提示の請求は試合中の議論をチェックするためのものであり、それを越えて、書面による判定の吟味を正当化するものではないのです。
よって、試合後の証拠資料請求はできるだけ早く行われるべきであり、資料の検討が終了した際には、ただちに競技者に書面を返却しなければなりません。ただし、証拠資料の違法性が問題となっていて、ジャッジによる協議が必要とされる場合は、例外的に証拠資料を留め置くことが許されます。
4.2 証拠資料の評価
§1 自由心証主義
証拠資料に関するジャッジの評価は、ジャッジが自由に行うことができます。これは、証拠資料に限らず、議論全体に妥当する原則です。証拠資料の判断という点では、ジャッジは証拠内容尊重の原則を元にして、証拠資料の文面や出典(権威性や発行年など)を材料にして総合的な判断を下すこととなります。このような評価プロセスの中でジャッジが拘束されるのは、ジャッジの良心と、公平性や思想中立性の要求といったディベートの基本原理、そして新出議論の禁止などのルールだけです。ですから、以上のような拘束に反しないのであれば、証拠資料の内容をどのように評価するかはジャッジの自由です。
証拠資料の評価は、相対的な観点からなされます。つまり、その証拠資料の試合全体における位置づけを踏まえた上で、その証拠資料にどのような評価を与えることが妥当であるかを考えるのです。ここで問題となるのは、当該証拠資料単独では証明力を問題なく肯定できるが、議論全体を通してみれば証明力が疑わしいという場合です。
典型的な例としては、立論で用いられた証拠資料の大部分が同一出典によるものであったという場合があります。このような場合、その立論は限られた立場からのみ正当化されるものであり、信憑性は低いと評価することが妥当です。ここからも分かるように、個々の証拠資料の評価とは別に、議論全体として証拠資料の証明力を減じることも許されているのです。証拠資料評価の自由心証主義は、このような意味――証拠資料の評価は議論全体で得られた心証をも考慮して決する――をも含んでいるのです。こうした考え方は、証拠資料が引用された論点にとどまらず試合における前提として機能するという観点からも理解することができます。
§2 証拠資料の要求程度
ディベートでは、証明を要する事実については、適切に証明がなされなければ評価しないということが原則です(立証責任の原則)。証明を要する事実というのは、端的に言えば主張全般を指すのですが、証明されなくても正しいと推定される経験則や一般常識、論理的帰結は、この例外にあたります。ここで問題となるのは、経験則や一般常識といった要素はどこまで認められるのか、いいかえれば、どこから証拠資料を用いた証明を要求されるのかということです。
これについては、ジャッジによって基準は全く異なりうることです。あるジャッジにおいては、証拠資料が無くても一般的に納得できる議論は一応の証明がなされたと推定するでしょうし、別のジャッジは、基本的な論点として提示された部分には全て客観的な証明がなされるべきであり、それが満たされない場合当該議論を評価することはできないと考えるだろう。このような違いは当然生じるものであり、これを排除することは不可能であるし、また望ましくもありません。審査基準の画一化は、議論を硬直化させ、実社会との乖離を強めるだけです。
しかし、証拠資料の要求程度はある程度の範囲で定められるべきだということも確かです。もし、証明の程度を非常に高くおいた場合、肯定側はほとんど勝つことができない状態に陥ってしまいます。逆に、全ての議論で証拠資料による証明を必要としない場合、議論の質が著しく低下し、教育的に望ましくない事態を招くかもしれません。
実際には、証明の要求程度は大会の種類や競技者のレベルによって、同一ジャッジの中でも異なって設定されます。初心者の試合では立証責任を過度に課さないよう配慮して判断することが教育的に望ましいのですが、一方で公式大会や上級者同士の試合では、試合の中で議論を尽くさせることが期待できる(そしてそれが選手の義務ともいえる)ため、公平性や議論の質の向上のために高い立証責任を負わせ、証拠資料により適切に議論を証明することが求められます。
ここで、試合ごとに評価の基準を変えるという見解もありえるところですが、それは選手の実力を熟知していることが前提となるし、たとえそうだとしても、同一大会で審査基準を変更することは公平性に欠けるので、基準変動は大会単位でしか許されないとするのが相当でしょう。しかし、前述のとおり、証拠資料の証明力は相対的に判断すべきものであり、その意味では大会の中においても判断基準に差異が生じることもあります40)。
§3 証拠資料の判断
それでは、証拠資料による証明を要求するとして、それが引用された資料によって適切になされたかどうかを判断する場合、ジャッジはどのように判断を行うべきでしょうか。具体的に問題となるのは、ジャッジが自由心証主義によって証拠資料の評価を否定することが可能であるかということです。
証拠内容尊重の原則によれば、ジャッジは当然に証拠資料の内容を評価し、本稿2.2で説明したような見地から証明力を判断することができます。しかし、試合においては証拠資料の評価もそれ自体争点となりうるのであり、選手にとって不意打ちとなる形でジャッジが証明力を判断する場合、弁論主義違反を構成する可能性もあります。
この問題をもう少し分かりやすく述べるならば、次のようになります。すなわち、証拠資料の内容そのものに問題がある場合は、証拠内容を評価した結果として、当然に自由心証主義が及ぶことになります。しかし、試合で提起されなかった見解や、経験則・公知に含まれないような情報によって証拠資料に批判を加えているような判断は、当事者の主張していない議論によって証拠資料の証明力を低く判断したことになりますから、証拠内容に独立に反論を加味したものとして許されません。
この二つの場合は連続的であり、極限事例においては微妙な判断となることがあります。別途議論を要する難しい問題であるため、ここで詳しく論じることは適切ではないでしょう。しかし、このような問題意識を踏まえて、証拠内容を判断することと証拠資料に批判的な意見を対置させることは別物であるという意識をもってジャッジに臨むだけでも、問題は少なくなるでしょう。
あとがき
本稿では、証拠資料の使用に関係する問題を検討してきました。その中には、実際に試合の中で問題となるような議論もあれば、どちらかというと例外的で、普段問題にされないし、問題になったとしてもその場の裁量で処理しうるようなものもあります。しかし、証拠資料を扱うにあたっておよそ考えうることを議論しておくことは、それ自体が実際のディベートの中で意味を持たないとしても、証拠資料という存在の意味を明らかにするという点で、何らかの意義を持つと思います。内容に関しては極めて稚拙なものでありますが、本稿がそのように読まれ、証拠資料についての理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
なお、本稿で扱った問題とそれに対する筆者の解答については、ディベート理論に関する諸文献がそうであるのと同様に、一つの考え方に過ぎません。つまり、証拠資料がどのような性質のものであり、どのように扱われるべきであるかということは、ディベートにおいて議論の判断が異なりうるのと同じく、それぞれのディベーターによって違う結論が導かれるものです。そのようなことを踏まえて、各ディベーターが証拠資料の扱い方について考え、より優れた議論を行うことに役立てていただければ、筆者としては至上の喜びです。
最後になりましたが、拙文をここまでお読みいただき、どうもありがとうございました。
2007年4月7日 愚留米
脚注
1)筆者の勉強不足から英語の文献は分からないのですが、本稿に関連する内容として、JDA-MLで過去に証拠資料の必要性に関係する議論がなされており、ダイジェスト版として公開されています。ここで議論されている内容は多少高度ではありますが、参照されることをおすすめします。
2)例えば、誰かに自分の想いを伝えるには、自分の言葉で語りかけるしかありません。「相手のことを愛している」証拠として、二十四時間相手のことを監視していた記録を提出することは可能でしょうが、筆者はお薦めしません。
3)他にもいくつか重要な原則はありますが、ここでは「証拠資料の意義」に関係する部分だけをあげておきました。
4)これは、ディベーターの個人的思想や権威付けによってスピーチを評価してはならないという意味(例えば、大学教授がディベートをしているからといってそのスピーチを肯定的に評価する材料にはならない)はもちろんのこと、ディベーターがいかに正しいことを言っていたとしても、前提とする常識を超える部分についてはさらなる客観的証明を求めるということを意味します。例えば、ディベーターが個人的に文献を読んで得た知識をスピーチしたとしても、それをそのまま採用することはできないということになります。本文で後述するとおり、証明を要する事実はあくまで証拠資料という客観的な根拠を用いて証明する必要があるのです。
5)もっとも、どの論点が重要であるかという判断は簡単なものではありません。ただ、論題についての資料を読む中で頻繁に触れられている部分や、個人的に疑わしいと思われる部分については、おそらく試合の中でも証明を要する部分であると考えることができるでしょう。
6)できる限りスピーチの中で議論させるということは、ジャッジの専門知識による恣意的な判定を少なくし、両チームが試合中にどのような議論をしたかによって判断する要素を高めるという点で、公平性を確保します。また、証明責任を求めることは試合における議論の質を高め、分析を深めることにもつながります。
7)証拠資料の著者がいかなる思想を持っているかが問題にされることは、ディベートでの議論評価は思想中立的であるという原則に反すると思われる方もいるかもしれませんが、それは違います。資料の著者の出典が問題にされるのは、著者の思想と資料にある議論の内容に整合性があるかどうかというような、あくまで客観的な見地による疑問があるときです。著者の思想と議論の内容が異なる場合は、議論の内容を著者は真にサポートしていないという推定が働き、その資料の証明力にマイナスの影響を及ぼします。また、特定の思想団体による、その思想に基づいた議論にはバイアスがかかっているだろうというような、一般的な推論もジャッジは考慮に入れることができます。一方で、ジャッジ個人の思想に照らし合わせて証拠資料(著者の思想も含める)を判断することは許されません。これらの論点については、本文(4.2)でも簡単に触れます。
8)ただし、ディベーターが明らかに適用する意志を持たないような交差適用などは弁論主義(当事者野主張によってのみ判定を下す)の観点から適用を控えるべきです。また、そのほかの場合でも、明らかに同一の論点が問題となっている場合や、矛盾が生じていて交差的に議論を判断しなければ整合性が取れないときなど、交差適用が必要かつ合理的であると考えるときに限ってジャッジの判断による交差適用がなされるのが望ましいでしょう。
9)これに対して、まずある論点について中身のある証拠資料が提出されていることを要求する(証拠内容の尊重)上で、交差適用についてスピーチ中の明示を要求しているのだから、形式のみを尊重するのではないという批判もあるでしょう。しかし、明らかに同じ資料が適用されるという論点について、交差適用が無いという形式的側面のみによって当該資料の適用を否定するという点については、やはり形式的に過ぎるような気がします。
10)しかし、交差適用が結果的に当事者の主張しない争点を形成する可能性にも注意しなければなりません。注8を参照。
11)簡単に言えば、タブラ・ラサとは、主張された議論をそのまま受け入れるという立場で、クリティック・オブ・アーギュメントは、議論のうちジャッジが納得できる内容のみを受け入れるという立場です。現在ではほとんどのジャッジがこの両者の中間をとり、介入の防止と教育的効果維持のバランスをとっていますから、あまり重要な論点ではないともいえます。つまり、反論が無かったからといって全部受け入れるといった立場はほとんどないということです。
12)ここでいう「誤った前提」とは、その内容が誤っているということではなく、そもそも存在しないのに存在しているものとして前提に加えようとしている誤りのことを指します。証拠資料の内容が正しいかどうかは試合中に客観的な見地から検討を加えられて決するものです。その結果、現実(いわゆる「真理」)の観点からは正しい内容が「誤り」と見なされることもありますし、その逆もあります。それはおかしいのではないかという疑問もあるかもしれませんが、これはあくまでその試合における議論応酬の結果を尊重するというディベートの枠組みに起因するものであって現実の政策形成や裁判においても(そして学問の世界においても)同様のことが起こっています。
13)この見地からは、選手個人がとったアンケートなどは証拠資料としては採用しがたいということになります。しかし、例えばディベート甲子園のルールではそのような資料も採用することができると読むことができます(ディベート甲子園ルール細則B・1項)。これは教室ディベートという特殊な環境に配慮した規定だと思われますが、競技としての見地からは疑問といわざるをえないでしょう。もっとも、このルールによっても「政府の公表した報告書などこれに準ずるもの」とありますので、何らかの形で公表された資料のみが証拠資料として使用可能だと限定的に解釈すれば、再現可能性の原則からも肯定できる帰結を得られることになります。
14)書籍や雑誌には発行者の名前(出版社など)を要求しないのにサイトには要求するというのは、ネット上のサイトは非常に不安定であるということから特別に要求できるということにあるでしょう。一方、紙媒体の場合は、一度発行されれば特別な場合を除いて消滅しないので、出版社などを要求する必要はないと考えられます。書籍の場合、該当部分の著者のほかに全体の編者が存在する場合がありますが、これについても「必須である」と考える必要はないように思われます(ただし、図書館での資料請求では編者――書籍の表紙に記載されている――を要求されるので、その見地からは必要といえるかもしれません)。もちろん、記録することが望ましいのはいうまでもありません。
15)これは、サイトの更新は一部分ごとに行われるため、いわゆるトップページに記載された更新日と当該ページの更新日が異なることも多い(そして、当該ページの更新日が欠けている場合が多い)という事情にもよります。
これに関連して、サイトの一部分の更新記録が、更新されていない部分に関してもその日付で内容を保証すると考えてよいかという問題もあります。書籍の改訂と同様、修正していない部分についても黙示の承認が与えられていると考えることもできますが、一般にサイト更新の際に他の部分について意識しているかといえば、難しいように思えます。ただ、認められないとするとインターネット資料の使用が困難になるということや、見解を変えたり間違いを認めたりした部分については積極的に更新するだろうと考えることも可能ですから、一部分の更新をもって他の部分の内容保証にあたると解しうるというのが筆者の見解です。
16)発表媒体も必要だということができるかもしれませんが、証拠内容尊重の原則から「要件」という強い形で要求できるのは、誰が発言しているかという点に限られると思われます。発表媒体などの要素は証明力の評価で問題にされれば足りるでしょう。
17)語源を知っているわけではありませんので、単なる推測に過ぎません。悪しからず・・・
18)時代の変化や研究の成果によって見解を修正・変更することはよくあることです。
19)もっとも、指示性の要求に関して言えば、年号を要求したところで同年に書かれた複数の文章が提示された場合には同一性を判断できなくなりますし、証拠内容に関しても、肩書きを要求しないのに年号を要求するというのはおかしいと考えることもできます。発行年を読みあげるのは一種の慣例となっているところもあり、本稿でもそれに従って発行年を要求しているのですが、最低限の出典としては発行年を要求する必要はないと考えることも可能でしょう。
20)そのほか、証拠資料の価値として、どの論点と特定することなく、ジャッジの視野や価値観を規定するという効果をあげることができます。もっとも、それについても特定の主張に基づいているという表現は可能ではありますが、試合のメタスタンダードを争う論点について「証明がされた」という表現が適切であるかどうかは、別途議論が必要でしょう。
21)これは、資料の弾劾一般にいえることです。発行年に関する論点や不適切な引用の項でも議論しているように、著者の真意がどのようであるかということは、証明力の評価についての一要素に過ぎません。文面上根拠があると思われる場合は、著者の見解と独立して評価しうるということができるでしょう。
22)前述の意味歪曲については、そもそも筆者が「その文章で」表現しようとしていたものとは異なる意味を作り出したという意味で問題があるのであり、著者の「現在の」思想に反するから違法であるという趣旨ではありません。著者の思想と、客観的な説得力は、議論内容による例外を除けば、異なる次元にあると考えられます。ただし、本文で挙げたイラク派兵の例を見てもわかるように、著者の意図軽視にあたる不適切な引用と許容される引用は、連続的に捉えられます。その境界線を画する要素としては、句読点の尊重や原典中における議論構成・配分のあり方などがありますが、これについては個々の事案に即して検討されなければなりません。
23)この同意は、相手方が証拠資料の違法について認識しており、さらにそれに対して積極的に同意していることを指します。また、「違法証拠使用による敗戦を宣告すべきで、そうでなければ違法証拠を自分側の有利となる論点に援用する」といった予備的主張における同意は認められないと解するべきです。
24)英語ディベートでは、過去に証拠資料の検証委員会が設けられたことがありますが、あまりのコストの大きさから、現在は活動していないようです。日本語ディベートで同様な制度を設けるとしても、そのコストは小さいものではありませんから、現段階では難しいと考えられます。一案としては、決勝戦などのトランスクリプト(速記録)を作成し、その一環として証拠資料の提出を求めるというものです。この方法は、証拠資料の事後検証と議論の記録という二つの目的を同時に達成することができます。ただし、これについてもコストの問題があることは否めません。
25)もっとも、これは立論中の証拠資料に限られるものであり、限界はあります。
26)ただし、対戦相手の同意が得られた場合は、前述した引用された側からの請求があったものと同視して、ジャッジの判断によって証拠調べを行うことができると考えられます。
27)これに対して、証拠資料の特定は証明力(証拠内容の実体的評価)ではなく証拠能力(その証拠資料を認めることができるかという形式的要件)の問題であるから、証拠能力の欠陥を補う(追完)することは新出議論と異なり認められるべきであるという議論もありうるかもしれません。しかし、形式的要件たる証拠能力の問題だとしても、それによって証明力を持った議論が突然現れるという意味では、新出議論と何ら変わりありません。そもそも証拠能力を欠いた証拠については証拠内容の評価をなすことができないことから、追完を認めたところで、その時点で「初めて」証拠内容を評価することになります。よって、後のステージにおいて特定がなされたとしても、最初に読んだ時の資料が評価されたと考えるのではなく、そのステージで新しく証拠資料が読まれた(新出議論に当たる)と解すべきです。
28)黙秘によってルール上のペナルティが課せられているということはありませんが、事実上はジャッジの心証として議論の信憑性が下げられるという不利益を受けます。なお、虚偽の応答を行った場合は、違法証拠排除の原則と同様に、該当する応答を無視するだけでなく、敗戦理由として処理することも可能だと考えられます。
29)逆に言えば、この点に「反駁における再度の言及」の意味があります。すなわち、ジャッジは再度言及されない場合は質疑の内容を採用しないことができますが、後のスピーチで言及された場合は、応答の信憑性に応じてその内容を判定材料として必要的に考慮しなければならないと考えることができます。すなわち、判定を説明する中で、当該論点についての質疑応答を踏まえた上での判断を示す義務が生じるということです。
30)一方で、ジャッジに関しては、聞き取った中で理解できた事項のみを判定材料にできると解するべきです。このこととジャッジの証拠調べの関係については、第4章で詳述します。
31)「先ほど読んだ全てのエビデンス」といった請求方法でも認められるということです。
32)逆に、常に原典の提示を求めるのであれば、再現可能性は常に担保されるのであるから、再現可能性を論じる必要はありません。再現可能性の原則とは、それが満たされる限りにおいて、別に存在する議論を援用することが許されるというものであり、この原則そのものが、原典そのものではない書面による証拠資料の取扱いを前提としているということができるでしょう。
33)もっとも、この見解には違法証拠の排除という観点が徹底されていないという批判が可能です。試合での利便性と違法証拠の排除という理念的問題の均衡を踏まえて、なお一層の検討が要される課題だと思われます。私見としては、現時点では競技者の良心を信用してよいのではないかと考えていますが、理想としては原典のコピーを整理して持参するなどの行為が行われることが望ましいでしょう。
34)ここで筆者の見解を簡単に述べておくと、競技ディベートのジャッジは教育的見地から選手と対等の立場を有しており、独立当事者として議論評価を通じて試合に積極的に参加する存在であると考えています。その帰結として、ジャッジには議論判定及びそこに至るまでの議論聴取の過程において公平性や客観性を損なわない範囲で積極的に自分の心証を開示する権利があり、またそれらの権利行使を通じて試合そのものを良い方向に導くという意味での教育性を発揮する義務があると考えます。こう考えることは本稿の内容を理解する上ではあまり関係ないと思われますので、詳しくは省略します。
35)訴訟法学における概念用語であり、簡単に言えば「裁判官は当事者の主張した内容に基づいて判断しなければならず、それ以外の材料を持ち出して判断することはできない」ということです(これに対する概念が「職権探知主義」です)。ただし、ディベートにおける弁論主義は法学用語としてのそれとは異なると考えられます。訴訟法上の弁論主義が妥当する範囲は「請求を構成する主要事実」と解するのが通説であるのに対し、ディベートでは主要事実たる投票理由の主張のみならず、それを支える根拠も含めて弁論主義が妥当すると考えられるからです。この点は別途議論を要するところであり、ここではこれ以上深入りすることは避けます。
弁論主義に関して付言しておくと、当事者が主張しない場合においてもジャッジの職権によって敗戦を宣告することができる場合もあります。本稿の内容に関係する例を挙げるとすれば、違法証拠の使用による敗戦などの規定を適用する場合です。この場合、違法証拠の使用は競技の枠組を害する問題であり、当事者の意思によらず罰するべきだからです。よって、相手当事者が違法証拠について同意したとしても、その証拠の使用に対する処分や証明力の減殺評価は否定されません。
36)職権探知主義がディベートにおいて一切妥当しないというのがディベート理論上の通説的見解だと思われますが、ジャッジを独立当事者として位置づける筆者のような立場(注34を参照)を前提とすれば、議論評価の枠組についてはジャッジの専権に委ねられており、弁論主義が排除されると解することができます。このように解するならば、議論評価の枠組について判断するために証拠調べを行うことができるという立場も理論的にはありうるところですが、ここでは疑問を留保しておきます。
37)蟹池陽一「Close-up さらに「ジャッジすること」に関して」ディベートフォーラム9巻4号(1994)の275p以下、特に276pを参照のこと。ただし、蟹池氏は引用された証拠資料全てについてジャッジが目を通せるようにするのが望ましいという見解を採られており、これは後に本文で示すように、筆者の見解とは異なります。蟹池氏はディベートの本質を議論の間の論理的連関と考え、議論の交換が口頭でなされていれば、議論の妥当性を示すための補助に過ぎない証拠資料は書面による確認でよいと主張されます。しかし、ディベートの本質が論理的連関にあるとしても、その要素をなす論証道具としての証拠資料も口頭で議論されるべきですし、証拠資料の中にも論理的連関が見られるはずです(そもそもディベートの本質について筆者は見解を異にしており、この点でも氏の見解には賛同できない点がありますが、これについては本稿では触れません)。実践的な問題としても、証拠資料だけが書面により評価されるとすれば、ディベーターは証拠資料をとにかく高速で引用して読んでしまえばよいということになりますから、口頭主義は事実上形骸化してしまいますし、そのような議論であればもはやスピーチという形式をとる必要はないでしょう(そのような形で競技を構成するというのなら別ですが)。
38)しかし、引用された証拠資料が極めて高い違法性を帯びる疑いがある場合は、対戦相手を保護する必要性もありますから、本文に挙げた配慮よりもジャッジの証拠調べが優先されるべき場面が生じうるところです。この場合にジャッジの証拠調べを許すかどうかは、試合途中にジャッジの判断で反則を言い渡すことができるかという問題とも関連して見解が分かれうるところであり、別途考察すべき問題でしょう。
39)この点、実務において証拠資料を過度に請求し、判定時に考慮するジャッジも存在するようですが、そのような行為は書面による判定の吟味によって弁論主義を潜脱するものというべきですから、厳に慎まれるべきです。
39)よく「前の試合では取ってくれたのに」といったコメントを聞きますが、議論の判断が自由心証によるものであり、大会の趣旨やレベル、議論の中における相対的価値といった多面的要素によって評価がなされることを踏まえれば、そういったコメントは的を射ていないということができます。